II 警防活動時等における安全管理マニュアル(各論)
§1 火災防ぎょ
1 破壊・進入活動
(1)破壊活動
ア 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 破壊活動は素手で行うと危険を伴うので、必ず防火手袋等を着用し、保護具や必要な資機材を有効に活用する。 |
▶ 注水障害のトタン板を素手で引っ張ったところ、トタンの縁で右手を負傷した。 |
2 破壊活動を行うときは、隊員相互に必ず声をかけ合い周囲の安全を確認してから行う。 |
|
3 破壊活動を行うときは、破壊器具を確実に保持する。また、必要に応じて器具に確保ロープを取る。 |
▶ 2階の窓ガラスを破壊した時、ガラス片が飛散し、地上で活動していた他の隊員にあたり、右手甲を負傷した。 ▶ とび口で羽目板を破壊中、とび口の柄が後方の隊員にあたり、顔面を打撲した。 |
|
4 破壊活動を行うときは、破壊衝撃による反動力でバランスを崩しやすいので、身体や足場の安定を図り、無理な体形動作をとらない。 また、高所及び不安定な場所では必ず命綱等を使用し身体を確保する。 |
▶ 破壊したドアを隊員が強く引いたところ、勢いあまってドアが倒れ、隊員が腰部を打撲した。 |
5 破壊活動を行うときは、正面及び下方を避けて位置し、防火帽のシールド、しころ等を活用して破片の飛散及び落下物による危険の防止に努める。 |
▶ 破壊する窓の正面に位置して窓を破壊したため、飛散したガラスに触れ、右手指を切創した。 ▶ 完全な防火着装をしないでエンジンカッターを使用したため、火花が胸元に入り火傷した。 ▶ モルタル外壁を破壊した際、粉じんが目に入り、角膜を損傷した。 |
6 荷重がかかっている部分を破壊するときは、破壊(切断)に伴う崩壊、落下物等に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
イ 窓、ドア等の開口部の破壊
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 ドア、窓等を破壊するときは、急激な火煙の噴き出しが考えられるので、必ず姿勢を低くして注水態勢を整えるとともに、側面に位置して必要最小限の範囲の破壊にとどめる。また必要に応じて、地上にも援護注水できる隊員を配置する。 |
▶ 積載はしごを利用して2階ベランダに進入し、施錠されているガラス戸を注水態勢が整わないうちに破壊したところ、急激に火勢が拡大し、顔面を火傷した。 |
2 延焼建物のシャッターを破壊するときは、火煙の噴き出しが考えられるので、シャッターの下部を切断するとともに、必ず注水態勢を整えておく。 |
|
3 窓、ドア等を破壊するときは、進入しようとする隊員と十分連絡をとり、安全を確認してから行う。 |
|
4 ガラスを破壊するときは、ガラスの重量及び厚さを考慮して窓枠の上部角から行い、また破片はできるだけ室内に落とすよう注意する。 |
|
5 はしご上からガラスを破壊するときは、ガラスの落下による受傷を防止するため、自らの位置は破壊する場所よりも高いところで行う。 |
▶ はしご上から筒先で頭上の窓ガラスを破壊したところ、飛散したガラス片で左手首を切創した。 |
6 進入路となる窓を破壊したときは、窓枠に残存するガラス破片を完全に除去する。 |
▶ 破損した窓枠に寄りかかり放水中、窓枠に残っていたガラス片に触れ、左手を負傷した。 |
7 ホースやはしご付近のガラスを破壊するときは、破片がこれらを伝って落下する危険があるので注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
ウ 屋根、壁体等の破壊
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 延焼建物の屋根に登って破壊活動を行うときは、屋根裏の延焼状況を十分確認し、むやみに歩かないようにするとともに、積載はしご等を活用し、その上を歩くようにする。 |
▷ 消火活動中、屋根伝いに移動していたところ、屋根瓦を踏み抜いて転落しそうになった。 |
2 屋根を破壊するときは、転倒・落下しやすいので、できる限り棟瓦をまたいで行う。 |
|
3 トタン板を剥がすときは、上部から順次行い、剥がしたトタン板は、切創等に注意して、とび口等の資機材で処理する。 |
|
4 屋根、壁体、天井を破壊するときは、噴き出してくる火炎で火傷するおそれがあるので、破壊部分からのぞき込まないよう注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
エ エンジンカッター等による破壊
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 エンジンカッターの切断刃の緩み、はずれに注意する。 |
|
2 エンジンカッターを使用するときは、切断時に生じる火花、切り粉に注意するとともに、防じん眼鏡等の保護具を使用する。 |
▶ エンジンカッターでシャッターを切断中、その切り粉が近くで待機していた隊員の目に入り負傷した。 |
3 エンジンカッターで破壊活動を行うときは、切断時の火花等による二次災害を防止するため、周囲に人を近づけない。 |
|
4 エンジンカッターは、駆動の状態で移動したり、他の隊員へ受け渡したりしない。また、エンジンカッターの刃は、停止・駆動に関わらず常に下を向けておき、人の方向に向けない。 |
▶ 駆動中のエンジンカッターを移動した際、つまずいて転倒し、切断刃で顔面を裂傷した。 |
5 壁等を切断した部分は、活動中の怪我防止や行動の障害とならないよう可能な限り折り曲げる等の措置を講じる。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)進入活動
ア 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 建物に進入する際は、昼間でも照明器具を携行する。 |
|
2 延焼建物に進入するにあたり、開口部を不用意に開放すると、火炎や濃煙等の噴き出しがあるので注意する。 |
|
3 一般火災であっても努めて呼吸器を活用するとともに、援護注水を受け複数の隊員で進入する。 |
|
4 火災状況の変化によっては脱出せざるを得なくなることを常に想定し、命綱、照明器具、ホースライン等を使用して必ず退路を確保する。 |
|
|
5 隊員は、進入前に相互に脱出予定時間を確認するとともに、進入後は時間の経過、空気ボンベの残量、脱出所要時間を考慮し、無理な行動をとらない。 また、警報ベルが鳴ったときは、直ちに相互に連絡し脱出する。 |
▶ 建物火災に出場し、人命検索活動中に負傷し、呼吸器の残圧がなくなり、一酸化炭素中毒により職員が死亡した。 |
6 延焼建物の内部へ進入するときは、他隊の放水や落下物、突起物等から顔面を保護するため、防火帽のシールド、しころ等を積極的に活用するとともに、できるだけ姿勢を低くし、手・足やとび口等で足元を確認しながら、壁体に沿って行動する。 |
▶ 火元建物に進入したところ、反対側で防ぎょしていた他隊の放水を受け、両眼を負傷した。 |
7 暗い場所に進入するときは、照明器具を必ず使用する。特に延焼している場合は、火災に気をとられがちであるので、足元に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
イ 積載はしご、地上物等を利用した進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 積載はしごは、落下や倒壊の危険のない場所に架ていする。 |
▶ 2階に進入する隊員のはしごを確保中、落下物が目に入り負傷した。 |
2 開口部に架ていするときは、濃煙等の噴き出しに注意する。 |
|
3 積載はしごを使用して進入するときは、架てい角度や荷重に注意する。 |
|
4 積載はしごを使用して進入するときは、横すべりやはずれによる転落を防止するため、はしご基底部の安定を図るとともに、必ず補助者に確保させるか、または手すり等にはしごをロープで固定する。 |
▶ 二連はしごを伸てい中、止め金具がロックされたと勘違いして、引き上げロープを離したところ、はしごがすべり落ち、確保者が右第1指を打撲した。 ▶ 架てい場所が不安定なうえ確保が不十分であったため、はしごが横すべりし、登てい中の隊員が転落し負傷した。 |
5 資機材を携行して又は背負ってはしごを登るときは、ロープやコード等の絡まりに注意する。 |
▶ 2階ベランダに架ていしたはしごに登はん中、ロープに絡まり足を踏みはずして転落し、腰部を負傷した。 |
6 積載はしごを登降するときは、足の踏み外し等による転落を防止するため、横さんを確実に握り三点支持を保つ。 |
|
7 窓から屋内へ進入するときは、燃え抜けに注意し、とび口等で足場の強度を確認する。また、できるだけ縁部を移動する。 |
|
8 アパートや事務所の窓際、ベランダには植木鉢等が置いていることがあるので、落下させないよう注意して進入する。 |
|
9 アーケードを利用するときは、転落を防止するため、設置されている消火足場以外からは進入しないようにする。 |
|
10 下屋、軒、物干台等から進入するときは、足場が腐食していることがあるので、その強度を確認して進入する。特に窓の手すりはもろい場合があるので注意する。 |
▶ 右手で物干台をつかみ進入しようとした際、物干台が腐っていたため折れ、転落し左でん部を打撲した。 ▶ 共同住宅火災において屋外通路の一部が腐食していたため崩落し、職員2名が転落して負傷した。 |
11 現場付近にある物品を活用して進入するときは、十分な強度と安全性があるかどうかを確認する。 |
▶ 付近にあった木製はしごを使って2階に進入しようとしたところ、横さんが折れて転落し、負傷した。 |
12 ブロック塀等を乗り越えて進入するときは、ブロック等の上に有刺鉄線やガラス片等盗難防止策が施されていることがあるので、不用意に登らないようにする。 |
▶ ブロック塀を乗り越えて進入しようとしてブロック塀に登った時、盗難防止用の鉄柵に接触し、左上腕を負傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
ウ 延焼建物に進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 放水開始前は、筒先員は内部に進入しすぎないよう注意するとともに、放水前であっても、筒先を確実に保持する。 |
▶ 隊員が、放水前に筒先を持って屋内に進入しすぎたため、炎にあおられ火傷した。 |
2 屋内に進入するときは、延焼状況を正確に把握し、必要に応じて援護注水を受けて進入する。 |
▶ 人命検索のため屋内に進入しようとした時、フラッシュオーバー現象による火煙の噴き出しにあい、気道に熱傷を負った。 |
3 屋内に進入するときは、障害物の状況・進入先の強度等をとび口等で確認する。特に、夜間及び濃煙中は視界が悪いので注意する。 |
▶ 作業場内に進入しようとした時、丸太につまずき、左アキレス腱を切断した。 |
4 階段を昇降するときは、すべりやすいので足元に注意する。また、廊下、階段等の曲り角での衝突に注意する。 |
▶ 屋内階段を上がり2階へ進入しようとした時、階段がぬれていたため滑り、転倒し右手を骨折した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
エ その他
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
木造密集地火災において建物間に進入するときは、火勢が回り込みや飛火等により退路を断たれるおそれがあるので、予備注水を行うとともに、監視要員を配置するなどの措置をとる。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 放水活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 筒先を移動するときは、周囲の障害物、落下物等に注意する。 |
▶ 筒先を移動するため、倒壊した鉄製アングル上を越えようとしたところ、バランスを崩し落差3.7mの隣地へ転落し、腰椎を圧迫骨折した。 |
2 濃煙等で足元が見えない場所においては、照明器具等を有効に活用する。 |
▶ 深夜、延焼建物周囲で放水中に転戦した時、側溝に足がはさまり、足首を捻挫した。 |
3 建物の老朽度、主要構造物の延焼程度、床面への瓦等落下物の堆積量、含水量及びほぞの噛み具合等を確認し、建物の倒壊や床の落下危険等の徴候を察知する。 |
|
4 焼き状況から判断して瓦、壁体、窓等が落下、倒壊の危険がある場合は、周囲の安全を確認してから棒状注水やとび口等で落下、倒壊させて危険を排除する。 |
|
5 筒先員は、放水の有無にかかわらず筒先を確実に保持し、特にノズルの開閉時は放水圧力による反動力が大きいので注意する。 |
▶ 筒先ストッパーで放水を停止した時、放水停止圧力の反動力のため筒先が胸にあたり、胸部を打撲した。 ▶ 筒先を移動しようとした時、急に放水圧力が高くなって筒先を保持できず手離したため、左顔面を強打し左下眼瞼を挫傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)延焼建物周囲からの放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、屋根瓦・モルタル等の落下・倒壊が予想される区域にロープを張り、現場の状況を拡声器、無線機等で全隊員に周知徹底する。 |
▶ 木造2階建の作業所火災において、トタン張り壁体の内部の間柱及び下見板が焼きにより炭化していたところに放水したため、放水圧力により落下したトタンが顔面にあたり負傷した。 |
2 防火造(木造)店舗併用住宅などの火災では、モルタル壁や化粧壁用パラペット(※)が崩壊する危険性が高いため、壁面付近で活動する際には十分留意する。 |
|
3 付近に送電中の電線や配線等がある場合は、感電の危険があるので、安全距離を保って放水する。 |
|
4 直近の壁体等に放水するときは、反動力が増加するので、筒先を確実に保持するとともに、足場を安定させる。 |
|
5 くぼみや障害物等が多い建物周囲では、足元を十分確認し行動する。 |
▶ 筒先移動を行う時、水のたまっていたくぼみに落ち、左足首を捻挫した。 ▶ 濃煙が急に噴き出したため、急いで後退したとき、くぼみに落ち、右大腿部を打撲した。 |
6 建物内部が燃焼しているときは、窓付ルームクーラー、看板等が落下するおそれがあるので、ルームクーラー等の真下での放水は避ける。 |
▶ 屋内に進入した際、居間の入口で破損して垂れ下っていたエアコンに顔面を強打し、前歯を折損した。 |
7 出火点が壁際の場合は、比較的初期の段階から壁体の落下、倒壊があるので注意する。 |
▶ 発災建物と隣接建物の間に進入し、放水を開始した時、建物の土壁が落下し、左肩を打撲した。 |
8 防火造建物火災において、モルタル壁に亀裂やふくらみが生じた場合は、はく離、落下等の危険に注意する。 |
▶ 放水中、モルタル外壁がはく離、落下し、頸部を捻挫した。 |
9 防火造建物火災においては、屋根瓦、モルタル等の落下、倒壊することの少ない建物の角に筒先を部署するか、安全な距離を確保する。 |
|
10 延焼建物に隣接する耐火建物の場合は、化粧モルタル、タイル仕上げの壁体は、加熱によってはく離、落下するので注意する。 |
▶ 延焼建物と耐火建物の間に進入して防ぎょ中、耐火建物が火炎にあおられ、モルタル壁がはく離、落下して顔面にあたり、鼻骨を骨折した。 |
11 材木置場は、材木支持材の初期燃焼により木材が崩れたり、倒壊したりすることがあるので注意する。 |
▶ 材木置場の横で防ぎょ中、突然木材が倒れ、その下敷きとなり死亡した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)積載はしご、屋根等の高所での放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 積載はしご上で放水するときは、強固な窓枠、手すり等にはしごの先端を必ずロープ等で結着するとともに、ガラスの破損、火煙の噴き出しに注意する。 |
▶ てい上放水中、はしごが横すべりして転落し、腰部を打撲した。 |
2 積載はしご上で放水するときは、必ず命綱等を使用して身体を確保するとともに、安定した作業姿勢をとる。 |
|
3 積載はしご上で放水するときは、放水圧力による反動力で転落しないよう、筒先又はホースをロープ等で結着する。 |
▶ はしごを外壁にかけて放水中、放水圧力による反動力で、はしごもろとも転倒し、背部を打撲した。 |
4 積載はしご上で注水方向を変換するときは、バランスを崩して転落することがあるので徐々に行い、特に筒先がてい体と直角になる横方向への変換は避ける。 |
|
5 屋根等の高所で放水するときは、余裕ホースを十分にとり、ロープで結着してホースのずり落ちを防止する。 |
▶ 屋根上でロープで結着しないでホースを延長したため、ホースが通水の重みでずり下がり、バランスを崩して転倒し負傷した。 |
6 屋根上は不安定であるため、放水圧力による反動力で転倒する危険があるので、前傾姿勢でかつ重心を低くして行う。 |
|
7 瓦屋根上で放水するときは、周囲の瓦をはずし、瓦さんを足場にするとともに、取り除いた瓦の落下防止を図る。 |
|
8 上記のほか、前記1 一般火災 2放水活動の(2)延焼建物周囲からの放水の留意事項1~3の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)延焼建物内での放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 頭上の落下危険物は、事前に棒状注水で排除する。 |
▶ 屋内で消火作業中、落下してきた瓦で背部を打撲した。 |
2 放水開始と同時に、濃煙が噴き出し、視界が悪くなったり、熱気に包まれることがあるので、いつでも移動できるように足元や周囲に注意し転倒防止を図る。 |
|
3 火点が視認できないときに放水すると、発煙量が増大して危険であるので、姿勢を低くして火点の確認に努める。 |
|
4 熱せられた壁体、天井、防火シャッター等へ放水すると、放水した水が高温水となって跳ね返ってくることがあるので注意する。 |
▶ 人命検索と放水を併行して実施中、壁体に放水した水が高温水となって跳ね返り、両手に第2度の熱傷を負った。 |
5 濃煙・熱気内で放水するときは、噴霧注水を行って排煙、排熱を図り、ふく射熱による熱傷を防止する。 |
|
6 出入口、廊下、階段等においては、ホースにつまずかないよう注意する。 |
▶ 屋内で放水中、ホースをまたいだところ、ホースにつまずき転倒し、右足を骨折した。 |
7 階段、廊下等は、燃焼により強度が低下し、踏み抜くことがあるので注意する。 |
|
8 室内の障害物は、とび口、放水等によって排除し、足元の安全を確保するとともに、床の踏み抜け、釘等の踏み抜きに注意する。 |
▶ 屋内で放水中、燃え残りの木材についていた釘を踏み刺創した。 ▶ 屋内で垂れ下がった電線につまずいて転倒し、胸部を打撲した。 ▶ 木造建物の2階で防ぎょ中に移動したところ、燃え残っていた床が抜け落ち1階に転落し、胸部を挫傷した。 |
9 部屋の中央部は床の抜け落ち、天井落下の危険があるので、部屋の角や窓際等で放水する。特に店舗等、間口の広い建物は、柱や耐力壁等が少ないため落下が早いので注意する。 |
▶ 木造店舗内で防ぎょ中、2階の床板が落下して左腕を負傷した。 |
10 落下物、床等の踏み抜けなどは火勢鎮圧後に多くなるので、ホースの撤収まで気を緩めることなく活動する。 |
|
11 木造大規模建物は、天井裏の火炎の伝走が速く、背後から急激に濃煙が襲うことがあるので、内部進入隊は相互に連携を保ち、弧立防止を図る。 |
|
|
12 放水銃等を使用するとき、高圧放水中の注水角度の変換は、反動力が大きいので、急激に行わないようにする。 また、放水銃を高圧で放水すると放水方向が、放水角度や地盤の状態によっては、自然に移動することがあるので、必要時以外は隊員を近づけない。 |
|
13 濃煙、熱気内での活動は、隊員の心身の疲労が激しいため、任務分担、各隊との連携、隊員の交代等に配意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(5)その他
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 工場、作業所等においては、水槽、溝等が放水した滞水によって視認が困難となることがあるので、筒先員はつま先で前方の障害物を検索しながら放水するか、または事前にロープ等で危険箇所を囲い、転倒、転落の防止を図る。 |
▶ 工場火災の防ぎょ中、側溝に転落し、筒先を手離したため、付近の隊員に筒先があたり、けい部を打撲させた。 |
2 鉄骨造建物のうち、柱、はり等に耐火被覆のないものは、加熱で変形・挫屈して倒壊するおそれがあるので、屋内活動及び建物直近での活動に注意する。 |
|
3 倉庫火災では、注水により内部の収容物が崩壊したり、棚板等の焼損により荷崩れ危険等があるので、進入は退路が確保できる範囲までとし、安全を確保するまでは、積荷間の狭い通路に部署しない。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 救助活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 救助活動を行うときは、複数で行動することとし、単独行動はしない。 |
|
2 火災現場で救助活動を行うときは、原則として呼吸器を着装するとともに、照明器具・ロープ等必要な資機材を有効に活用し安全の確保を図る。 |
|
3 火災現場は、落下物、床の抜け落ち、壁体等の崩壊、火煙の噴き返し等があるので注意する。 |
|
4 救助活動を行うときは、援護注水を受けて進入するとともに、退路の確保を図る。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)呼吸器の着装
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 呼吸器を着装するときは、必ず進入前に気密点検及び警報ベルの作動点検等を確実に行う。 |
|
2 隊員は進入前に、相互に脱出予定時間を確認するとともに、進入後、呼吸器の警報ベルが鳴ったときは、直ちに相互に連絡し脱出する。 |
|
3 進入するときは、常に脱出所要時間を考慮し、無理な行動をとらない。 |
|
4 呼吸器を着装しているときは視界が悪いので、足元や周囲の状況等に注意する。 |
▶ 呼吸器を着装した隊員が階段を降りた時、他の隊員と接触してホースにつまずき、右足首を捻挫した。 |
5 呼吸器の面体は、安全な場所に脱出するまでははずさない。 |
▶ 呼吸器の面体を安全な場所に脱出する寸前にはずしたため、濃煙を吸い、失神転倒し負傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)人命検索
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、火災の状況、建物内部の状況、要救助者の有無等を把握し、隊員に対して適切な指示を与える。 |
|
2 指揮者は、隊員を屋内へ進入させるときは、進入隊名及び隊員数等を確実に把握する。 |
|
3 人命検索は原則として照明器具等を携行し、複数の隊員が協力して行動する。また、必ず退路を確保するとともに、命綱を身体に結着する。 |
|
4 延焼建物の濃煙内で検索するときは、足元を確認のうえ姿勢を低くして、必要に応じて援護注水を受けて行う。 |
|
5 火煙のない場合でも延焼危険が大きい場所や煙の滞留が予想される場所では、急激な延焼拡大や噴き返しに注意し、迅速に検索を行う。 |
▶ 2階を検索のため階段を上がりかけたところ、急激な火炎の噴き出しで顔面を火傷した。 |
6 上階を検索するときは、階下の延焼状況を十分に把握するとともに、足元の強度を十分に確認し、床等の踏み抜きに注意する。 |
▶ 火元建物の2階を検索中、階下が焼きによりもろくなっていたため、床が落下し階下へ転落し負傷した。 |
7 落下危険のある瓦、ガラス等は他の隊員等に注意しつつ、事前に棒状注水やとび口等により落下させる。 |
▶ 2階へ上がるとき、瓦が落下し、頭部を打撲した。 |
8 破損している窓枠にはガラス片が残っていることがあるので、不用意に触れない。 |
▶ 検索中、窓枠を握ったところ、窓枠に残っていたガラス片で右手指を切創した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)要救助者の救出・搬送
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 火災現場で各種資機材を応急的に使用するときは、補強を十分に行い、二重、三重の安全措置を講じる。 |
|
2 要救助者を救出、搬送するときは、余分なロープ等が足に絡まるなどの危険があるので、その処理を完全に行う。 |
▶ 要救助者を搬送中、階段で余分なロープ等に足をとられ転落し、肩を打撲した。 |
3 要救助者を救出、搬送するときは、バランスをとり、不安定な姿勢にならないようにするとともに、周囲の障害物に注意する。 |
|
4 火煙等で視界が悪い場所では、救出姿勢は特に低くするとともに、つまずき、すべり、踏みはずし等の危険があるので、足元に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
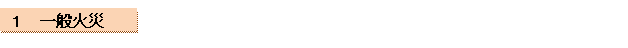
一般に防火造や木造の店舗で、通りに面した部分だけ屋根を隠すように外壁を立ち上げた部分