1 破壊・進入活動
(1)破壊活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 窓、壁体を破壊するときは、火煙の噴き出しによる二次災害を防止するため、進入、注水、排煙等の破壊目的に応じた開口の大きさとするとともに、注水態勢を整えておく。 |
|
2 高所で破壊活動を行うときは、十分な足場を確保し、命綱等により身体を確保するとともに、とび口や掛矢等を使用するときはバランスを崩さないようにする。 |
|
3 高所で破壊作業を行うときは、破壊物の落下の危険があるので、地上の隊員と連絡をとり、危険範囲を明示する。 |
▶ 積載はしごを使用し登はん中、はしごの確保者と連絡をとらず、2階の窓ガラスを破壊したためガラスの破片が確保者の手に落下し負傷した。 |
4 レンガ造、ブロック造の壁体は、破壊により他の部分も崩れやすくなるので、他の隊員を周囲に近づけない。 |
|
5 重機等での外壁破壊による開口部の設定は、建物倒壊の危険があるため、柱等の主要構造部の破壊は避ける。 |
|
6 倉庫等での上階の床面の局部破壊は、濃煙熱気層を増加させるおそれがあるので避ける。 |
|
7 上記のほか、前記1一般火災1破壊・進入活動(1)破壊活動のア 共通事項の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)進入活動
ア はしご車、隣接建物等を利用しての進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 はしご車等により高所から進入するときは、必ず命綱等により身体を確保して転落の防止に注意するとともに、はしご車のバスケットやリフターから延焼建物へ進入する場合は、延焼建物との間隔やバスケットやリフターの揺れに注意する。 |
|
2 はしご車等により高所から進入するときは、頭上にある高圧電線には特に注意する。 |
|
3 かぎ付はしご、ロープ等を使用するときは、堅固な支持物を利用する。 |
▶ かぎ付はしごのフックを朽ちた窓枠にかけたため、登てい中に窓枠が崩壊し転落、全身を打撲した。 |
4 バルコニー、ベランダの手すり等は、とび口などで強度を確かめてから利用する。 |
|
5 タラップから進入するときは、足を踏みはずさないよう安定した姿勢をとるとともに、常に両手で横さんをしっかり握って行動する。 |
|
6 隣接建物から進入するときは、転落を防止するため両方の建物間にロープを展長し、はしごを縮てい状態でかけ、命綱等で身体を確保して慎重に渡る。 |
|
7 上記のほか、前記1一般火災 1破壊・進入活動 (2)進入活動のア 共通事項の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
イ 延焼建物への進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
| ① 共通事項 | |
1 指揮者は、火災の実態、建物内部の状況、出動部隊等を把握し、適切な状況判断のもとに主要進入路を設定し、特に避難者との競合を避ける。 |
|
2 昼・夜間とも照明器具を積極的に使用し、足元等の安全を確保するとともに、階段の昇降時や廊下、階段等の曲がり角での衝突に注意する。 |
|
3 店舗やホテル等で透明ガラス、鏡等のある場所は、錯覚しやすいので進入するときに注意する。 |
|
4 非常用エレベーターを利用するときは、火点階より1階層下の階に進入し、火点階には直行しないようにする。 |
|
5 倉庫等の建物の主要構造部に耐火被覆のない鉄骨材を使用している場合は、火災時の高熱により挫屈や湾曲による建物倒壊の危険があるので注意する。 |
|
|
6 倉庫等は、収容物(毒劇物、危険物、指定可燃物等の危険物品及び可燃性物品)や収容形態(冷凍、定温、燻蒸、流通、自動ラック、トランクルーム等)により、火災の性状及び消防活動上の危険性・困難度が異なるため、事前把握している情報や関係者からの情報に注意する。 また、倉庫火災は収容物によっては爆発の危険もあることから、原則として収容物が確認できるまで、内部進入を避ける。 |
|
7 冷凍倉庫や低温倉庫等は、断熱材としてウレタンフォーム等を使用しているものがあり、爆燃や燃焼拡大、また不完全燃焼による一酸化炭素等の有毒ガスの発生などの危険があるので注意する。 |
|
8 冷凍(冷蔵)倉庫等の冷媒に、フロンガスやアンモニアガスが使用されており、漏洩による中毒又は酸欠の恐れがあるので注意する。 |
|
9 冷凍(冷蔵)倉庫での冷温状態では、煙が上昇せず、下階に拡散されるおそれがあるので注意する。 |
|
10 倉庫等の建築材として、断熱材(ポリウレタン等)を金属製薄板で挟み込んだ建築材料(サンドイッチパネル)を使用している場合、状況によっては爆発的に異常燃焼を起こす危険性があるので、十分に注意する。 |
▶ 断熱材(ポリウレタン等)を金属製薄板で挟み込んだ建築材料(サンドイッチパネル)を使用している倉庫での火災で、急激な濃煙熱気の発生後、強烈な火勢となり、職員が死亡した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク | |
| ② 濃煙内への進入 | |
1 指揮者は、あらかじめ進入目的、内部構造、火煙の状況、退出時間、連絡方法等を隊員に指示し、進入時間及び呼吸器の充てん圧力等を確認させるとともに、進入隊名と人員を確実に把握する。 |
|
2 隊員は、必ず呼吸器を着装し、呼吸器の面体の着装は濃煙内に進入する直前に行うとともに、濃煙内では有毒ガスが含まれているおそれがあるため、呼吸器の面体は絶対に外さない。 |
▶ 呼吸器が濃煙・熱気のためくもってしまい、いったん呼吸器の面体を離脱して延焼状況を確認しようとしたところ、高熱を直接両眼に受け火傷した。 ▶ 煙が内部に吸い込まれる状況のため呼吸器の面体を着装しないで進入したところ、急に煙が吹き出しため脱出しようとしたが、方向を誤り、意識を失って転倒し、救助隊に救出された。 |
3 進入隊の編成は必ず複数隊員とし、命綱等で身体を結着して進入し、活動中は絶対に単独行動はとらない。また、外部に命綱等の確保者をつけ進入隊員の安全を図ることを原則とするが、支持物等に結着するときは、支持物の強度、周囲の状況等を確認して確実に行う。 |
|
4 隊員は、常に脱出経路を念頭に置き、命綱、照明器具、ホースライン等を使用して退路を確保する。 |
|
5 隊員は、進入前に相互に脱出予定時間を確認するとともに、進入後は時間の経過、空気ボンベの残量、脱出所要時間を考慮し、無理な行動をとらない。また、警報ベルが鳴ったときは、直ちに相互に連携して脱出する。 |
|
6 必ず照明器具を携行し、できれば二重の照明を確保する。 |
▶ 人命検索のため3階に進入したが、濃煙・熱気に加えて照明器具を携行しなかったため、障害物につまずき、右前腕部を捻挫した。 |
7 投光器を使用するときは、コードは活動の支障とならないように壁体沿いに延長するとともに、結合体(コネクター)が抜けないよう措置する。 |
▶ 製材所の火災現場にて夜間消火活動中、挽き粉を溜めておくピット(約3m四方、深さ2m)内に水が貯まり地面と区別が出来なくなったため、転落した。 ▶ 濃煙内で援護注水を受けて人命検索中、投光器のコードが身体に巻き付いて倒れ、顔面を火傷した。 |
8 隊員は、姿勢を低くして壁体等に沿ってすり足で足元を確認しながら進入する。なお、燃焼により壁体等が高温になっていることがあるので、注意する。 |
|
9 広い場所に数隊が進入するときは、相互の衝突を避けるため、とび口等で床を叩いたり、拡声器や無線等を活用して、隊員間の所在を明らかにしながら進入する。 |
|
10 自閉式防火戸から進入するときは、途中で閉鎖しないよう、とび口等で退路に必要な幅員の開口を確保する。 |
|
11 2系統以上の階段があって、吸気及び排気階段に分かれているときは、吸気側階段から進入する。 |
|
12 濃煙・熱気内に進入するときは、不用意に立ち上がると熱傷するおそれがあるので、低い姿勢で活動する。 |
|
13 倉庫の資材搬入口がプラットホーム(高床)になっている場合があるので、転落に注意する。 |
▶ 濃煙が充満し視界を失い、資材搬入口から転落し負傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク | |
| ③ 火点階、火点上階への進入 | |
1 進入前に防火衣と呼吸器の着装状態を確認し、特に素肌を露出させないようにする。 |
▶ 防火衣の後ろ襟部分に、天井部分から落ちてきた高熱の熱湯が入り、熱傷を負った。 |
2 筒先員は、放水開始前に内部に進入しないよう注意するとともに、筒先を確実に保持する。 |
|
3 火点階等に進入するときは、避難階段、避難器具等の設置位置を確認して脱出手段を確保する。 |
|
|
4 火災室等のドアやシャッターを開放するときは、フラッシュオーバー現象やバックドラフト現象(※1)等による火煙の噴き出しの危険を避けるため、ドアの側面に位置し、注水態勢の完了を待って徐々にドアを開放し、内部の様子を見ながら進入する。 |
|
|
5 火点上階に進入したときは、可能な限り窓を開放して排煙を行うが、火点階からの噴炎がスパンドレル(※2)やダムウェーター(※3)等により上昇している場合は、火煙を室内に呼び込むおそれがあるので開放しない。
※2 スパンドレル
火災の延焼を防ぐため、耐火構造等の防火区画を構成する床、壁、防火設備が接する外壁を、当該部分を含んで90cm以上の部分を準耐火(耐火)構造としたもの。 ※3 ダムウェーター食品など物品を運ぶための小型エレベーター。 |
▶ 火点上階に進入し、窓を開放したところ、火点階の噴炎がスパンドレルより上昇し、顔面を火傷した。 ▶ ゴミ処理場での消火活動中、ベルトコンベアー上から立ち上がっていた炎が急に消えた直後、急激に高温熱気に包まれ周囲が見えなくなり、退避ができず、職員1人が死亡した。 |
6 ガス爆発した高層共同住宅の壁体、手すり等は亀裂破壊などにより強度が低下しているので不用意に進入しない。 |
|
7 倉庫内で収容物が高く山積みされている場合は、焼き等により荷崩れの危険があるため、狭い場所への進入や活動には注意する。 |
|
8 上記のほか、前記(2)進入活動 イ 延焼建物への進入①及び②の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)その他
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 延焼建物の周囲で活動するとき及び内部へ進入するときは、ガラス、モルタル壁等の落下物に注意する。 |
▶ 狭い路地ではしごを搬送中、頭上からガラス片が落下し、背部にあたり刺創した。 |
2 火災室の一部を破壊し注水口を設けるとき、またはてい上放水するときは、内部進入の各隊と十分連絡をとり、安全を確認してから行う。 |
▶ はしご車隊が不用意に屋外から窓ガラスを破壊したところ、火炎が一挙に拡大し火災室内の防ぎょ隊員2人が火傷した。 |
3 投光器を使用するときは、発電機は原則としてつまずき等の障害とならない屋外に置くが、やむを得ず屋内で使用する場合は、一酸化炭素中毒を防止するため換気の措置を講じる。 |
|
4 工事中の建物で壁や手すりのない廊下、階段を利用するときは、ロープを展長し転落の防止を図る。 |
▶ 火元建物に隣接する工事中の建物の階段踊り場で消火活動中、転落の防止措置を講じていなかったため、注水方向の変換の際誤って前に踏み出し1階に転落、右肋骨を骨折した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 放水活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 建物内は、放水活動により床・階段等が水浸しとなり、滑りやすくなっているので、足元に注意する。 |
|
2 上記のほか、前記1一般火災 2放水活動の(1)共通事項の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)はしご車等による高所での放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、落下・倒壊が予想される区域にロープを張り、拡声器、無線機等で危険防止を全隊員に周知徹底させる。 |
|
2 付近に送電中の電線があるときは、感電の危険があるので安全距離を保って放水する。 |
|
3 てい上放水するときは、必ず命綱等を使用して身体を確保し、無理な体形動作をとらない。 |
|
4 てい上の筒先員は、機関員とインターホン等を使用して連絡を密にし、状況の変化に対応できるようにする。 |
▶ てい上で放水中、昇ってきたリフターに接触し左大腿部を挫傷した。 |
5 てい上の筒先員は、開口部からの濃煙の吹き出し等による危険を回避するために、必ず呼吸器を着装し、放水活動にあたる。 |
|
6 開口部の正面から放水すると、火炎、濃煙の噴き出しによって熱傷等を負うことがあるので、側面から放水を行う。 |
|
7 てい上で放水中に注水方向を変換するときは、放水圧力の反動力によりバランスを崩す危険があるので徐々に行い、特に筒先がてい体と直角になる横方向への変換は避ける。 |
|
8 高圧放水をしているときは、直近の壁体等に放水すると反動力が増加し、バランスを崩すので足場を確保する。 |
|
9 上記のほか、前記1一般火災 2放水活動の(1)共通事項の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)延焼建物内に進入しての放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 延焼中の室内に注水するときは、開口部から火炎とともに高温の水蒸気が噴き出してくることがあるので、開口部側面から行う。 |
▶ 延焼中の室内へ放水を開始したところ、激しく高温の水蒸気が噴き出し顔面に熱傷を負った。 |
2 高温の室内に進入するときは、火煙等の噴き出しにより熱傷の危険性があるので、できる限り二段構えの放水隊形をとり、後方隊は前方隊を援護注水する。 |
|
3 コンクリート内壁は、急激な加熱の場合または部材厚が薄い場合は、最盛期になると受熱により爆裂や崩落するおそれがあるので注意する。 |
|
4 二方向に開口部を設定し、排気側から放水するときは、吸気側に火煙の噴き返しがあるので、吸気側の隊と連絡をとり、安全を確認してから行う。 |
|
5 劇場、体育館、映画スタジオ、工場、倉庫等の天井には、照明器具、装飾品、荷役機械等があるので、落下に注意する。 |
|
6 劇場、映画館等の床は、傾斜、段差があるので、転倒またはつまずかないよう足元に注意する。 |
|
7 キャバレー、ナイトクラブ等の階段の手すりは、構造的に弱いものもあるので注意する。 |
|
8 機械室、ボイラー室等の床は、油がしみ込み滑りやすいので足元に注意する。 |
▶ 高窓から屋内進入した際、床に付着していた油で足がすべり転倒し腰部を打撲した。 |
9 倉庫は、荷崩れや爆裂等の危険があるので、退避できる安全距離を確保して放水を行う。 |
▶ 三連はしごに登り放水中、注水により段ボール原料の梱包の山が崩れ、はしごもろとも転倒し、梱包の下敷きとなり負傷した。 |
10 無窓建物や冷凍倉庫等密室に近い室内火災の場合は、酸欠状態になっていることが多いので、必ず呼吸器を着装して進入する。 |
|
11 壁体が熱せられ、剥離する危険のある場合は、安全な距離を保持し、真下での放水は行わない。 |
▶ 準耐火建物の工場火災で、火炎がおよそ5m離れた耐火建物の壁体に噴きつけ、壁体の化粧タイルが隊員の足に剥離落下し、右足関節を骨折した。 |
12 倉庫内では、高く山積みされた収容物により、延焼範囲の確認が困難であり、かつ無効注水になりやすいので注意する。 |
|
13 大規模な倉庫火災等で現場活動が長時間に及ぶ場合は、熱中症等の予防を考慮し、交代要員の確保や水分と塩分の補給等に配慮する。 |
|
14 石造り、れんが造りの建物は、一部が崩れると未燃部まで一挙に崩壊する場合があるので、十分注意する。 |
|
15 上記のほか、前記1一般火災2放水活動の(4)延焼建物内での放水の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 救助活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 建物内は、放水活動により階段や床等が水浸しとなり、滑りやすくなっているので足元に注意する。 |
|
2 上記のほか、前記1一般火災 3救助活動の(1)共通事項の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)呼吸器の着装
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
前記 1一般火災3救助活動の(2)呼吸器の着装の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)人命検索
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 耐火建物内に進入して、人命検索を行うときは、内部構造が複雑な場合が多いので、順序よく効率的に行い、重点箇所を最優先に行う。 |
|
2 屋内進入して人命検索を行うときは、原則として援護注水を受けて活動する。 |
▶ 援護注水を受けないで進入したところ、要救助者の救出直前に室内が急に炎に包まれ火傷した。 |
3 排煙のための開口部を設定するときは、急激な延焼拡大、または煙の流動の急変による危険があるので、各隊と連絡を密にし、安全を確認してから行う。 |
|
4 複雑な進入路は、曲がり角に強力なライト等を固定し、退路の確保を行う。 |
|
5 耐火建物内では煙が薄くても一酸化炭素中毒のおそれがあるので、呼吸器の面体をはずさない。 |
|
6 破損している窓枠には、ガラス片が残っていることがあるので、不用意に触れない。 |
|
7 上記のほか、前記 1一般火災3救助活動の(1)共通事項の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)要救助者の救出・搬出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 はしご車を利用して、高層ビルから要救助者を救出するときは、要救助者に急にしがみつかれたり、飛びついてくることがあるので注意する。 |
|
2 要救助者を背負い搬送するときは、足元を確認し、安定した足場を選んで降りる。 |
|
3 上記のほか、前記1一般火災3救助活動の(4)要救助者の救出・搬送の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(5)その他
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 避難者と進入隊員が交錯するときは、指揮者は両者の安全を確保するため進入隊員を統制する。 |
|
2 避難誘導を行うときは、誘導員は避難者のパニック状態に巻き込まれないよう注意し冷静に行う。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
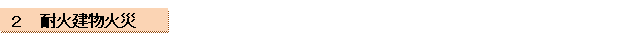
気密性のよい室内等において酸素不足のため燃焼が衰え、炎が消えたり、くすぶったりして可燃ガスが充満しているところに、開口部等の空気の流通があると可燃ガスが爆発的に燃え窓等から火炎が噴き出す現象。