1 進入行動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 原則として、風上側に部署し、有毒ガスが発生するおそれのある火災の場合は、必ず呼吸器等を着装して活動する。 |
|
2 事業所正門等安全な場所で、関係者からの情報収集を行い、不用意に構内へ進入しない。 |
|
3 指揮者は、関係者と密接な連絡をとり、火災の状況、危険物等の特性である爆発危険や有毒性の有無等を的確に把握し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して適切な指示を与える。 |
|
4 指揮者は、危険物の流出、爆発、引火、気象条件等により火災の様相が急変しやすいので、不測の事態が発生することを念頭において、進入路、注水部署を指示する。 |
|
5 事業所には、危険物のほか、高圧ガス、毒劇物等を貯蔵または取扱っていることが多いため、二次災害発生の危険が大きいことに特に注意する。 |
|
6 二次災害の防止や人命安全のため、退路を念頭に置いて活動する。 |
|
7 指揮者は、燃焼中または延焼のおそれのある危険物について、爆発、引火、有毒ガス発生等の危険性が判明したときは、速やかに隊員に周知徹底を図り二次災害の防止に努める。 |
▶ アクリル酸エステル合成工場の配管結合部から抽出液(アルコール、アクリル酸2―エチルヘキシル、ニッケルカルボニル等の混合物)が漏出炎上中、消火活動にあたっていた隊員がニッケルカルボニルを吸入して中毒になった。 |
8 隊員は、常に事態の急変に備え、臨機応変の措置がとれる態勢で活動する。 |
|
9 危険物火災は、一般的に燃焼速度が速く広範囲に高温の放射熱を発生するため、耐熱服、呼吸器等の着装または援護注水等の遮熱措置を講じる。 |
|
10 危険物火災は、火面が一挙に拡大したり、爆発する危険が大きいので、一挙に進入することを避け、火災や周囲の状況を確認しながら、地物を利用して進入する。 |
|
11 事業所には、塔槽類、配管等が輻輳して設置及び敷設されているので、頭上や足元の障害物によるつまずき、転倒、衝突、転落等に注意して進入する。 |
▶ プラント火災の消火活動中、地上に敷設された配管につまずいて転倒し、腰部を打撲した。 |
12 ガソリン、アルコール等の液状危険物は、引火性が高く速燃的であるので、火炎の伝搬、放射熱等に十分注意して活動する。 |
|
13 ニトログリセリン、硝化綿、ピクリン酸は、加熱、衝撃により爆発危険があるので、所要の距離をとり放水砲、放水銃等を活用して冷却すること。 |
|
14 火災が拡大し、指揮権を委譲する場合は指揮宣言等を行い、指揮権が委譲したことを周知徹底し、厳格な統制をとる。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)引火、爆発性ガス気内ガス滞留区域内への進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、燃焼物の種類、数量、気象条件等から判断し、検知器を活用してガス濃度の測定を行い、速やかに警戒区域(ガス濃度が爆発下限値の30%を越える区域)を設定して出場全隊員に周知徹底を図るとともに、二次災害防止のため区域内の火気の使用禁止及び隊員の立入を制限する。検知器の標準ガスの較正は、警戒区域外の正常な空気のある場所で行う。 |
▶ 可燃ガスもれ現場で漏えい箇所を調査中、残留ガスが爆発し、隊員が火傷した。 |
2 身体の露出部分を可能な限り少なくする。 |
|
3 ガス滞留区域内に通じる電気配線の電源スイッチの遮断及びガスの元弁の閉止を確認してから進入する。 |
|
4 火花を発するおそれのある携帯無線機、投光器等を携行しない。 |
|
また、エンジンカッター、ガス溶断器等の火元となる資機材を絶対に使用しない。 |
|
5 原則として風上側、地形の高所側から噴霧注水によりガスを希釈または拡散しながら進入するとともに検知器により安全を確認する。 |
|
6 ガス気内に進入する場合には、爆発に伴う爆風圧、飛散物等による被害を防止するため、マンホール、側溝、窓や出入口などの開口部、ブロック壁体付近に部署することを避け、耐火建物等の遮へい物を活用して進入する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 放水活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 放水活動中、各隊は相互に連携を密にし、事故防止を図る。 |
|
2 放水活動をするときは、爆発により倒壊危険のある壁体間、または高所には部署しない。 |
|
3 危険物火災は、急激な火炎拡大または爆発の危険が大きいので、放水銃(砲)等を活用して二次災害の防止を図る。 |
▶ 危険物倉庫の火災で、消火活動にあたっていた隊員が、二次爆発のため顔等を火傷した。 |
4 原則として風上側から防ぎょ活動を行うが、防油堤等のない施設の場合は、特に風上側、高所側から行動し、風上側と高所側が異なるときは風横側から行動し、流出油の延焼に注意する。 |
|
5 長期間高圧放水を行うときは、支持物に筒先を結着する等して転倒の防止を図るとともに、体力の消耗を軽減する措置を講じる。 |
|
6 危険物の貯蔵、取扱い場所は、階段、床面等に油が付着していることがあり、転倒、転落の危険があるので、足元に注意して行動する。 |
|
7 放水活動による滞水、または、泡の被覆で付近の側溝、ピット等の所在が視認できなくなるおそれがあるので、事前に警戒テープ等で表示し、転倒、転落を防止する。 |
▶ 常圧蒸留装置火災で放水活動中、泡被覆により溝に気付かず転倒し、ひざを負傷した。 |
8 泡消火薬剤等でいったん消火しても、時間の経過、風の影響等により再燃することがあるので注意する。 |
|
9 金属ナトリウム、金属カリウム、カーバイド等の禁水性物質は、注水により可燃性ガスを発生し、爆発燃焼するので絶対に注水しないこと。 |
|
10 マグネシウム粉、アルミニウム粉等の金属粉又は金属の切りくずが燃焼中のときは、注水により爆発を伴って燃焼するので、絶対に注水しない。 |
|
11 指揮者は災害の状況や放水等の活動による災害拡大の抑制効果を的確に判断し、必要により隊員を退避させるなど二次災害防止に努める。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)タンク火災の消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 火災タンク内の危険物を他のタンクに移し替えるときは、安全に移送可能な状態であることを確認して行う。また、空気の流入等により火勢が強まることがあるので注意する。 |
|
2 防油堤内は危険性が大きいので、原則として資機材等を設置する場合を除き進入しない。 |
|
3 ベント、放爆構造等が常に有効に作用すると過信しない。反応の状況等は一様でなく、予想できない爆発形態をとることがあるため注意する。 |
|
|
4 冷却注水を行うときは、スロップオーバー現象(※1)が生じるおそれがあるので、タンク内部に放水しないようにする。 また、泡放射を行う場合でも、原液の劣化、発泡不良、放射中断等があるとスロップオーバー現象を生じるおそれがあるので注意する。 |
|
5 冷却注水を行うときは、タンクの側板等から跳ね返った高温水により、熱傷を受けないよう注意する。 |
▶ 屋外タンク火災で、隊員がタンクを冷却するため側板に放水中、跳ね返った高温水のため、他隊員が熱傷した。 |
|
6 タンクの側板塗料の変色、冷却注水の蒸発状況から熱波の下降状況を把握して活動する。 熱波がタンク底部に近づくと、ボイルオーバー現象(※2)により火面が一挙に拡大するおそれがあるので注意する。
※2 ボイルオーバー現象
注水によりタンクの下部に貯まった水が、その後の燃焼で温度が上がり沸騰しタンクから水蒸気とともに燃焼している危険物が急激に噴き出す現象をいう。 |
|
7 タンクの側板、脚部等が加熱された場合は、わん曲、座屈を生じて倒壊する危険があるので、冷却注水に配意するほか、火災の状況及び周囲の工作物の状況に応じて安全な場所で活動する。 |
|
8 放水活動中に防油堤内に消火及び冷却水が滞水したときは、タンクからあふれた危険物が一挙に延焼拡大して放射熱や火炎にあおられる危険があるので堤内の滞水は、適宜防油堤外に排水する。 |
|
9 火災時における流出油は、高温になっていることが多いので、触れて熱傷を負わないよう注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)プラント火災の消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 高度化・複雑化したプラントにおいては、専門的な知識と経験を有する事業所から積極的に情報収集を行う。 |
▶ アクリル酸精製塔の廃液を貯蔵するアクリル酸中間タンクが、異常な温度上昇により爆発炎上し、25名が死傷した。 |
2 延焼により二次爆発を起こす危険があるので、不用意な接近を避けるとともに、放水銃(砲)を活用するなど、隊員の危険防止に配意する。 |
|
3 不意の爆発により破片等の飛散等が考えられるので、堅固な地物、工作物等を遮へい物にするなど危険の防止に努める。 |
|
4 爆発火災の場合は、配管、各種機器等の破損箇所の飛散片による受傷に注意する。 |
▶ 石油化学コンビナート製造プラントの貯蔵タンクが炎上し、隣接タンクの爆発で飛散した破片により隊員が負傷した。 |
5 容器内の液化ガスが火災により加熱され、又は内圧が上昇して膨張している可燃性液体タンクは亀裂により、BLEVE(ブレビー)現象(※3)を起こすこともあるため、関係者等から情報収集を行うとともに、爆発による受傷に注意する。 |
|
6 塔槽類、送油管等から可燃性液体及び気体が流出、漏えいし引火したときは、爆燃を伴うことが多く、しかも防油堤がない場合には流出油等が短時間に広範囲に拡散し、火災が拡大する危険があるので注意する。 |
|
|
7 消火により爆発危険がある場合は、周囲の圧力容器・配管等を放水により冷却するとともに、施設関係者等と連携して、漏えい系統のブロック化、脱圧、窒素置換の実施について配慮する。
※3 BLEVE(ブレビー)現象
塔槽類等の容器内の液化ガスが火災により過熱され、内部圧力が上昇した容器を破り気化した時点で着火したとき、爆発的な燃焼を起こす現象。BLEVEは、Boiling Liquid Expanding Vapour Explosionの頭文字を取ったもの。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)タンクローリー火災の消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 燃焼実体への接近は、耐熱服の着装、固定物等による遮へい及び援護注水を受けて行う。 |
|
2 流出した油が炎上しているときは、放水すると火面が拡大するので、泡消火薬剤等を活用し火面を拡大させない。 |
▶ 不用意に放水したため、流出した油の火面が一気に拡大し、手足を火傷した。 |
3 筒先を保持する隊員は、急激な火炎拡大に対して、速やかに退避できる位置で活動する。 |
|
4 泡で覆われた地表面の歩行時には、転倒・捻挫等に留意する。 |
|
5 泡で覆われたマンホールや下水溝等には、警戒テープ等により明示する。 |
|
6 地下室・地下街、共同溝・洞道及び下水・側溝等への着火油、未着火油及び蒸気の流入に留意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(5)ごみ固形化燃料施設等火災の消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 関係者から適宜情報を収集し、必要に応じて大量放水による消火又は不活性ガスの注入などによる消火を行うなど、火災の状況に応じた最も効果的な措置をとる。 |
|
2 RDF貯蔵槽などにおいては、温度上昇による爆発危険性があるため、貯蔵槽天板における放水活動はしない。 |
▶ RDFの貯蔵サイロで異状発熱及び爆発があり、消火活動中に爆発により2名が死傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(6)その他の火災の消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 油槽所でタンクローリーの充てん中における火災の場合は、数台のローリーが同時に充てんを行っていることが多いので引火に注意する。 |
|
2 流出油火災の場合は、側溝へ油が流出して思わぬ地点で延焼する危険があるので注意する。 |
|
3 ガス噴出火災の場合は、消火することによって可燃性ガスが広範囲に拡散し、爆発炎上するおそれがあるので、むやみに消火せず、関係者とともに、バルブ閉止を確認後、消火活動を行う。 |
|
4 野積みのドラム缶やタンクローリー等の火災の場合は、タンク鏡板面(平らな側面)が爆発により飛散するおそれがあるので、必ずタンク胴板面側から活動する。 |
|
5 硫黄粉等を収容した建物火災は、粉じん爆発の危険があるので、噴霧注水により爆発の防止を図る。 |
|
6 加熱されたドラム缶等を移動するときは、十分に冷却した上で衝撃を与えないように十分注意する。 |
|
7 メチルエチルケトンパーオキサイド等の過酸化物は、加熱や衝撃により分解爆発のおそれがあるので、遮へい物等を利用し、かつ安全な距離を確保する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 救助活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、火災の状況、燃焼危険物の特性、特に爆発危険、有毒性の有無等を的確に把握し、隊員の安全確保のため、必要な指示を行うとともに、進入隊名と隊員数を確実に把握する。 |
|
2 必ず呼吸器を着装するとともに、状況によっては、耐熱服を着用し、行動中は絶対に単独行動をとらないようにする。 |
|
3 放射熱や爆発危険による二次災害の防止のため、堅固な地物、工作物等を遮へい物に利用し、かつ援護注水を受けて活動する。 |
|
4 火煙や放射熱のない場合でも、災害の様相が急変しやすいので、常に臨機応変の措置がとれる態勢で迅速に活動する。 |
|
5 救助活動中、無理な体形動作をとらないとともに、頭上や足元の障害物による衝突、転倒、転落等に注意する。 |
|
6 上記のほか、前記 2耐火建物火災3救助活動の(1)共通事項、 (2)呼吸器の着装、(3)人命検索、(4)要救助者の救出・搬送及び (5)その他の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
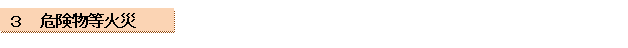
燃焼している石油等の危険物の温度が高い場合、注入すると水が急激に沸騰しタンクから水蒸気とともに燃焼している危険物が急激に噴き出す現象をいう。