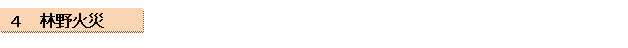1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 林野火災においては行動範囲が非常に広く、長時間にわたり不案内の地形での活動を余儀なくされるため事故を起こしやすいので、指揮者は火災の規模、発生時刻、発生場所の地形及び山林の状況、気象条件、消防防災ヘリコプター(消防航空隊)からの偵察情報等を的確に把握し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な注意と指示を与える。 |
|
2 林野火災においては、できる限り消防防災ヘリコプターによる空中消火を行い、特に起伏の激しい山中における消火活動には空中消火を用いる。 |
|
3 林野火災は、行動範囲が広く、延焼状況の把握が困難であるので、統制ある部隊活動を行う情報連絡体制の確立に配意する。 |
|
4 林野火災は、地形が悪く、強風・乾燥等の悪条件下での活動となる場合が多いので、服装は保安帽、編上げ靴など活動しやすいものを着用する。 |
|
5 山の急斜面を延焼中の場合や強風等で急速に延焼拡大中の場合は、非常に危険なので、上方または風下側に部署せず、燃えた跡地や防火帯、大規模な空地等から監視する。 |
▶ 火勢も弱く安全と判断して出発し、火点から上方約50m地点に部署したところ、風向きが急変して斜面に沿って延焼拡大したため、山腹を横切るように焼け跡めがけて退避したが逃げきれず、16人が死傷した。 ▶ 現場進入し防火帯を構築していたところ、突風により火勢が襲い、全身熱傷により死亡した。 ▷ 林野火災現場において火炎が突然の強風によってあおられ延焼拡大し、活動中の消防隊員が巻き込まれそうになった。 |
6 気象条件(風向・風速)の変化により延焼状況が急変する場合があるので、活動中、休憩中を問わず、監視員を置き、常に延焼状況の把握に努めるとともに、必ず退路を確保する。 |
|
7 林野火災に出動する隊は、通常の活動と比較して疲労が蓄積するため、水筒や塩分補助食等を持参して、適宜水分補給等を行う。 |
▷ 長時間の防ぎょ活動で、必要に応じた給水ができなかったため、熱中症になりかけた。 |
8 原則として住宅の隣接地を除き山地の林野火災は、日没後には消火活動を行わない。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 進入活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、行動前に高所より火勢、地形等の状況を観察し、風位風速等の気象条件から延焼速度、延焼方向等を把握し、火勢に追われても十分退避可能な距離を保った進入路を選定するとともに、防ぎょ方法、安全確保等の必要事項を具体的に指示する。 |
|
2 山林は地理不案内なことが多いので、危険防止のため地理精通者を案内人として進入する。 |
|
3 指揮者は、進入隊名及び隊員数を確実に把握するとともに、高所に監視員を配置し、適宜連絡をとって進入隊の所在を常に把握する。 |
▶ くまざさや雑草の繁茂した雑木林火災で、風下に部署して付近一帯の防火線構築作業中、監視員を置かなかったため、突然熱風と煙に包まれ火中を突破したが、10人が死傷した。 |
4 進入隊は、指揮本部及び高所監視員と連絡を密にし、部隊の孤立等危険な状態に追い込まれないよう注意する。通信連絡が途絶し視界が狭く状況判断ができないときは、燃えた跡地や防火帯、大規模な空地等へ後退する。 |
|
5 各種資機材を持って進入するときは、保護カバーを使用し、安全に保持して、つまずき、転倒の際の受傷を防止する。 |
|
6 進入路のはっきりしない山林は、布切れを枝に結ぶ、立木の皮をはぐ、枝を切って立てるなど目印をつけて退路を確保して進入する。 |
|
7 しの、しだ、かや等の原野、切り落とした下枝を放置した山林は、急速に延焼が拡大する危険があるので進入しないようにする。なお、やむを得ず進入するときは、必ず退路を確保する。 |
|
8 延焼が2方向に分かれたときは、その間は火災にきょう撃されて極めて危険な状況に陥るので進入しない。 |
|
9 進入はできる限り焼け跡や稜線を選び、谷間には進入しないようにする。 |
|
10 傾斜地では落石、焼き物の落下、飛火の危険があるので、燃えている真下から進入しないようにする。やむを得ず進入する場合は、高所監視員等と連絡を密にする等、十分注意する。 |
|
11 地形の悪条件、障害物等による疲労を防止するため、急激な移動は避け適宜休憩をとる。なお、休憩するときは、監視員を配置し努めて林道等安全な場所を選ぶ。 |
|
12 樹木の枝、切り株等の突出物が多いので、つまずき、すべり、転倒、踏み抜き等に注意する。 |
▶ ホース延長の際、木の枝先が目にあたり、右目を負傷した。 ▶ ホース背負器がつるに引っかかり転倒、左肘部を負傷した。 |
13 急傾斜面を降りるときは、隊員の滑落防止のため、立木等を利用して確保ロープを設定する。 |
▶ 林野火災に際し、夜間で極めて危険な場所に降りようとした時に、バランスを崩し50m下に転落し、脳挫傷により死亡した。 |
14 杉、ひのき等の植林地に張ってある木起こし用の針金は、枝葉に隠れて視認しにくい場合が多く、顔面等にひっかける危険があるので、気付いた隊員は布切れ、木の枝等をかけて後続隊員の注意を喚起する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 消火活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、常に延焼速度、方向等の状況の急変を予想し、避難路を考慮のうえ部隊配置を行う。 |
|
2 指揮者は、長時間にわたる防ぎょの場合は、隊員の疲労度を考慮し、休憩、現場交替等を適切に行うよう配慮する。 |
|
3 消火活動は、孤立による危険を避けるためできる限り複数隊で行い、携帯無線を効果的に活用する。 |
|
4 単独行動は極めて危険であるので行わない。必ず複数の隊員で相互に声をかけ合い、その声が聞こえる範囲内で行動する。 |
|
|
5 隊員は延焼状況、風向の変化に注意して行動する。 また、急斜面では上方及び風下側の延焼速度が速く危険であるので特に注意する。 |
▶ 防火線設定完了後、燃え下がり部分に進入しようとした時、突然風向が変わり後方に飛火したため退路を断たれ、18人が死亡した。 |
6 晴天の昼間の火災は、炎が見えにくいので注意する。 |
|
7 夜間の火災は、危険が非常に大きいので原則として活動しない。やむを得ず活動する場合は、照明器具等を活用し、安全管理に十分配慮する。 |
|
8 火災の前線が200mないし300m前方であっても延焼危険帯と判断して、事態の急変に備える。 |
|
9 側面や後方へ飛火したとき、送水が中断したとき、あるいは火炎は見えないが強い熱気、熱風を感じたときは、危険であるので退避する。 |
▶ 延焼状況の確認後、部署を定め防ぎょ中、飛火及び風向の急変で急速に延焼が拡大し、監視員が大声で連絡したが延焼のごう音で届かず、しかも足元が枯枝に埋っていたため避難が遅れ、火煙に巻かれて4人が死亡した。 |
10 高圧線付近が延焼しているときは、火炎により断線した高圧線で感電するおそれがあるので注意する。 |
|
11 個人装備の完全着装を徹底する。特に、顔面等の露出部の防護については十分に配慮する。 |
|
12 イノシシ等の動物、マムシ等の毒蛇、スズメバチ等の昆虫類及びうるし等のかぶれを生じる植物には十分注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)傾斜地での活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 傾斜地は、落石や転落の危険があるので注意する。特に焼け跡の下方は、落石等の危険が大きいので注意する。 |
|
2 傾斜地の上方で行動するときは、下方に隊員がいることを考慮し、不用意に物を落とさない。 |
|
3 落石を生じさせたときは、または落石あるいは落石のおそれのある状況を視認したときは、大声で下方の隊員に危険を知らせる。 |
|
4 傾斜地では焼き物や焼け石等が火の粉を飛散させながら落下し、下方に飛火するおそれが大きいので注意する。 |
▶ 山頂から谷間に飛火し、異常乾燥と吹き上げる突風のため、一瞬のうちに延焼が拡大して火災が斜面を上昇したため、中腹で消火活動中の隊員が避難することができず、焼死した。 |
5 傾斜地に沿って燃え下がっている火災の場合は、火勢拡大に伴って上昇気流がおこり、延焼方向が急変することがあるので注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)注水による消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 背負い式水のう(可搬式散水装置)で消火するときは、延焼や飛火等により退路を断たれる危険があるので、周囲の下草等に予備注水をしながら行動する。 |
|
2 傾斜地上方でホース延長により注水を行うときは、火煙、気象等の状況を考慮し、隊員の安全を確認してから行う。 |
|
|
3 延焼、風向等の状況が急変することを念頭において、余裕ホースを十分にとって行動する。 また、急斜面に延長したホースが放水等によりずり落ちるおそれがあるときは、ロープで立木等に結着する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)火たたきによる消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
火たたきによる場合は、無雑作に行うと周囲に火の粉が飛散し、火災を拡大させ、退路を断たれるおそれがあるので、未燃部から延焼してくる火災に向って行う。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(5)覆土による消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
覆土の下の火災は容易に消火されず、再燃することがあるので注意する。 |
▶ 林野火災をいったん消火したのち、再燃火災に備え警戒を実施中、再出火した火災が突風にあおられ、急速に拡大したため警戒中の隊員が逃げ遅れ死亡した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(6)迎え火による消火活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 迎え火による場合は、延焼拡大の危険性が高いので、地形、山林の状況、気象条件等を考慮して慎重に行う。 |
|
2 迎え火を行うときは、十分な防火線と多数の警戒員等を配置し、関係隊員が相互に連絡を密にして行う。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(7)伐開防火線設定活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 チェーンソー等の資機材を使用するときは、安定した足場を確保し、資機材を確実に保持する。伐採するときは、周囲の隊員の状況を確認してから行う。 |
▶ 小雨で湿っていた丸太に乗り伐採木の枝払いをしていたところ、足がすべって転落し、持っていたチェーンソーの刃が足に触れ負傷した。 |
2 斧や鎌等の資機材を使用するときは、柄が抜けて受傷する危険があるので、事前点検を行うとともに、使用中においても適宜点検を行い安全を確認する。 |
|
3 斧、鎌等を地上に置くときは、踏みつけて受傷する危険があるので、切株等に打込んでおくようにする。 |
|
4 資機材を使用して伐採するときは、周囲の隊員の状況を確認してから行う。特に付近で他隊員が伐採しているときは、立木の長さの2倍以上の間隔をとる。 |
|
5 裂けた木を切るときは、木片が飛散して受傷する危険があるので注意する。 |
|
6 防火線の設定により延焼阻止が可能となった場合においても、飛火により防火線を突破して延焼することがあるので、鎮火するまで注意を怠らない。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(8)避難
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、気象条件の変化等により延焼状況が急変したときは、延焼の方向、風向、地形等を考慮して避難路を決定し、速やかに隊員に指示をする。 |
|
2 火勢や煙の流れを見定めて避難の時機、方向を冷静に決定する。特に火災が斜面を上ってくるとき、または山腹を横に燃えてくるときは、上方へ逃げると危険であるので注意する。 |
|
3 避難路を決定するにあたっては、火勢の弱い方向、または燃えた跡地や防火帯、大規模な空地等を選ぶようにする。 |
|
4 指揮者は、速やかに隊員の確認を行い、統制のとれた避難行動に努める。 |
|
5 隊員は相互に協力して冷静に避難する。 |
|
6 隊員は、避難するときは自衛に必要最小限の資機材(スコップ、なた、背負い式水のう等)を携行することとし、避難に負担となる資機材は後続隊員の障害にならない場所に放置する。 |
|
7 煙に包まれたときは、あわてることなく新鮮な冷たい風が吹いてくる方向に避難する。 |
|
8 ぬれタオル等で口や鼻を覆って、煙や熱気を直接吸わないようにするとともに、姿勢を低くしてくぼ地などで身を守り、周囲に注意して脱出する。 |
|
9 不測の事態の発生に備えて、体力に余力を残しておく。 |
|
10 落雷には十分注意する。活動現場近くで落雷が発生した際、少しでも雷撃傷の症状がある場合には、のちに重症となった症例があるので、必ず病院へ行く。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |