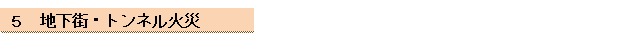1 破壊・進入活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 地下鉄・地下街、トンネル火災においては、特に密室性が高く、濃煙・熱気等がたちこめるなど活動上の障害が多いため、指揮者は、関係者から消防活動上必要な情報を収集するとともに、火煙の状況、内部構造、進入の安全性等を的確に把握し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な指示を与える。 |
|
2 指揮者は、現場を把握するため、防災センターや交通管制室等に設置されている監視テレビ、各種消防用設備等を積極的に活用する。 |
|
3 破壊・進入活動を行うときは、濃煙・熱気による危険を防止するため、排煙設備を活用して強制排煙を行うとともに、防煙区画の排煙口を利用して自然排煙を効率的に行う。 |
|
4 指揮者は、進入目的、内部構造、火煙の状況や連絡方法等を隊員に指示し、確認させるとともに、進入隊名と人員を確実に把握する。 |
|
5 呼吸器の面体は、濃煙内進入直前に確実に事前点検を行ってから着装し、進入後は空気ボンベの残量に注意して、警報ベルが鳴ったときは直ちに脱出する。なお、トンネルの場合でも、活動時間と往復に要する時間を念頭におき、余裕をもって脱出する。 |
▶ 工事事務所の職員2名が、トンネル工事現場で火災が発生し、10数名が逃げ遅れたとの通報を受けて救助に向かったが、呼吸器の使用可能時間を十分確認しないで進入したため、2名とも脱出できず、窒息死した。 |
6 進入は必ず複数隊員で行い、命綱を結着してロープで退路を確保するとともに、照明器具を携行する。 |
|
7 濃煙・熱気の噴き出しにより、火点の確認や内部進入が極めて困難となるので、必ず援護注水を受けて進入する。 |
|
8 この種の火災は外気に直接面していないため、煙の発生が極めて多く、しかも有毒ガスが発生し充満することが多いので、火災室内はもちろん排煙口付近においても十分注意して行動する。 |
|
9 密閉状態の室の扉、シャッター等の開放または破壊は、バックドラフト現象によって火災が拡大し、隊員に危険を及ぼすおそれがあるので、火勢に対応できる注水態勢を整えてから行う。 |
|
10 燃焼区画への進入は、落下物・倒壊物を放水やとび口等により排除したのち、低い姿勢で壁体に沿って行うとともに、つまずき・転倒や衝突に注意する。 |
|
11 附室や消防隊専用進入口から燃焼区画等に進入するときは、防火戸開放による附室や消防隊専用進入口への煙の流入に注意する。 |
|
12 上記のほか、前記 2耐火建物火災の1破壊・進入活動の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)地下街 (地下鉄駅舎部分を含む。)
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 地上への煙の噴き出しがわずかであっても、地階には濃煙が充満し、熱気、有毒ガス、酸欠空気が広範囲に滞留しているので、必ず呼吸器を着装し、十分注意して進入する。 |
▶ 煙が見えなかったので面体を着装せずに進入したところ、酸欠空気が充満していたため活動困難となり、他隊員に救出された。 |
2 地上から地階へ吹き込む風は、一定せず変化しやすいので、風向と風速に注意する。 |
|
|
3 特に階段等を使って進入するときは、避難者との衝突に注意する。 また、地下駐車場の車路から進入するときは、避難車両等に注意する。 |
|
4 地下鉄・地下街がビルに連絡している場合は、煙道作用によって地上階へ多量の煙等が流出し延焼拡大の危険があるので、進入路を設定するときは十分注意する。 |
|
5 地下鉄・地下街は、数棟のビルと連絡していたり、通路や間仕切が複雑になっていることが多いので、必ず退路を確保して進入する。 |
|
6 地下鉄と接続している地下街火災の場合は、電車の運行によって煙の流れが変わるおそれがあるので、必ず地下鉄駅舎との接続部分の扉の閉鎖を確認する。 |
|
7 地下街火災は、活動範囲が広く階段を使用するため、体力の消耗が著しくなるので、つまずきや転倒に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)トンネル(地下鉄、列車・自動車用)
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 地下鉄・列車用トンネルは、電源の遮断または運行列車の停止措置を必ず確認してから進入する。 |
|
2 ホームからの転落に注意するとともに、線路へ降りるときは十分足元に注意する。 |
|
3 地下鉄等の軌道上を進入するときは、線路、枕木、側溝等につまずかないよう注意する。 |
▶ 地下鉄の駅から進入するとき、不用意にホームから飛び降りたため、線路につまずき転倒し負傷した。 |
4 トンネル内の濃煙・熱気を避けるため、消防隊専用進入口(立坑)や避難口のある場合は、これを有効に活用する。 |
|
5 上下線が区画され、災害発生車道(線)の反対車道(線)に進入することが可能な場合は、濃煙・熱気による危険を防止するため、反対車道(線)から進入する。この場合、必ず車両(列車)の停止措置を確認する。 |
|
6 災害発生車道(線)から進入するときは、噴煙の流れ等から風向を確認して風上側から行う。なお、熱気流、有毒ガス、酸欠空気が滞留しているので十分注意する。 |
|
7 火災の最盛期のトンネルは、火災が火流となって天井等を伝走するので注意して進入する。なお、火炎で熱せられたコンクリートは、はく離落下するので注意する。 |
|
8 自動車用トンネルの場合は、自動車燃料等の危険物による火災が主体であるので、ふく射熱が強いことを念頭において行動する。 |
|
9 自動車用トンネル内のタンクローリー火災等の場合は、流出油等により瞬時に延焼が拡大するおそれがあるので、慎重に行動する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 放水活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 長時間防ぎょを行うときは、隊員の疲労を考慮し、交替要員を確保する。 |
▶ トンネル火災において、長時間継続して作業をしたため疲労度が増し、めまい及び吐き気を訴え、脱出したが酸素欠乏症となった。 |
2 特に地下深層部で放水するときは、地上との高低差があることから筒先での圧力が増すので、機関員は高低差を考慮して送水するとともに、放水員は確実に筒先を保持し、ゆっくり筒先を開放する。 |
|
3 急速に延焼が拡大するおそれのあるときは、状況に応じた援護注水を行う。 |
|
4 化粧タイルやモルタル壁等は、急激な加熱によって最盛期に爆裂、落下するので注意する。 |
|
5 延焼区画内等では、放水活動を行うにあたっては、事前に落下物・倒壊物を棒状注水やとび口等で排除するとともに、足元の安全を確認して行動する。 |
|
6 灼熱した防火戸、シャッター、車両、列車等に放水するときは、放水した水が熱湯となって跳ね返り、熱傷することがあるので注意する。 |
|
7 上記のほか、前記 2耐火建物火災の2放水活動の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)地下街(地下鉄駅舎部分を含む。)
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 延焼区画内に放水するときは、噴き返しの危険があるので注意する。 |
|
2 地下街には、衣料品・皮革等延焼しやすい物品を取り扱っている店舗が多いので、火炎・有毒ガスの発生に十分注意して行動する。 |
|
3 二酸化炭素消火設備を活用するときは、要救助者や活動隊員の有無を確認してから密閉し操作する。 |
|
4 地下街の通路は、放水によりすべりやすいので、筒先を確実に保持し、転倒しないよう十分注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)トンネル(地下鉄、列車・自動車用)
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 地下鉄車両、トンネル内の列車火災や電気施設火災の場合は原則として電源遮断(パンタグラフの降下)を確認してから放水を行うが、緊急やむを得ないときは、感電のおそれのない安全距離をとって噴霧注水を行う。 |
|
2 爆発の危険があるときは、人道や反対車道(線)に退避できる位置に部署し、待避所や消防隊専用進入口を防護体に利用し、できる限り低い姿勢で行動する。 |
|
3 急速に延焼が拡大している火災は、高熱で活動が困難であるので、熱傷防止のため放水銃(砲)を活用する。 |
|
4 熱気内での放水は、熱湯の跳ね返りによる熱傷の危険があるとともに、水蒸気の発生で蒸風呂状態となり、疲労が倍加するので注意する。 |
|
5 架線等は、火災の熱で切れて、垂れ下っていることがあり、感電の危険があるので触れないよう注意して行動する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 救助活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、関係者と密接な連絡をとって内部構造、火災の状況等の必要事項を把握するとともに、常に救助隊の行動を把握する。 |
|
2 人命検索は、必ず複数隊員で行い、進入にあたっては呼吸器を着装し、命綱を結着してロープで退路を確保するとともに、照明器具を携行する。進入後は空気ボンベの残量等に注意し、余裕をもって脱出する。また、面体は不用意に離脱しない。 |
|
3 濃煙・熱気が充満しているので、姿勢を低くして噴霧注水により排煙を行うとともに、援護注水を受けて行動する。 |
|
4 電源が遮断された場合、足元が不安定となるほか、隊員の不安感が増すので十分な照明を確保して行動する。 |
▶ 照明器具を携行せず進入して救出活動中、電源が遮断されたため、暗闇の中で行動し、転倒して負傷した。 |
5 排気側から救助活動を行うときは、火煙の噴き出しが激しいため、援護注水の態勢を整えてから行う。また、吸気側も噴き出しの危険があるので、吸気側から救助活動を行うときは、相互に連絡を密にして行う。 |
|
6 人命検索が広範囲にわたるときは、重複検索や疲労による事故を防止するため、担当範囲を指定する。また、隊員は、退路を見失うおそれがあるので、担当範囲内において行動し、絶対に単独行動をとらない。 |
|
7 避難誘導を行うときは、避難者がパニック状態に巻き込まれないよう投光器、メガホン等の資機材を活用して避難者の恐怖心を取り除くよう配意する。特に、パニックになった要救助者に抱きつかれて自由を奪われることもあるので、慎重に行動する。 |
|
8 検索場所は、倒壊や落下した障害物が散乱しているとともに、濃煙により視界が悪いので、つまずきやすべり、踏みはずし等に注意して行動する。 |
|
9 濃煙内の救出は姿勢を低くし、無理な態勢で行動しない。 |
|
10 上記のほか、前記1破壊・進入活動の留意事項及び 2耐火建物火災の3救助活動の留意事項の例による。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)地下街(地下鉄駅舎部分を含む。)
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 複層階地下街の場合は、通路が迷路のようになっているため方向がわからなくなる危険があるので、壁体または延長ホースに沿って行動する。 |
|
2 各店舗にはショーケース、商品、看板等があるので頭上や足元に注意して衝突、つまずき、転倒を防止する。 |
▶ 地下ショッピングモールで救助活動中、落ちてきた看板が腕にあたり負傷した。 |
3 濃煙のため、階段等から転落しないよう注意する。 |
|
4 階段を使用して進入する場合、避難者との衝突に注意する。また、地下駐車場の車路から進入する場合は、避難車両等に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)トンネル(地下鉄、列車・自動車用)
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 通行車両や運行列車の停止を必ず確認してから行動する。 |
|
2 外気等の状況によって突然風向が変わることがあるので、進入時に煙が薄いからといって呼吸器を着装しないで進入しない。 |
|
3 軌道上は線路、枕木、側溝等の段差があって足場が悪いので、つまずきや転倒に注意する。 |
▶ ホース延長中、枕木を踏みはずして右足首を捻挫した。 |
4 長大トンネルの場合は、待避所、連絡通路、立(斜)坑等があるので、トンネル内の濃煙・熱気を避けるため、これらを有効に活用する。 |
|
5 地下鉄等の火災は、感電をおそれて早期に電源を遮断することは、照明を失った乗客の不安感を助長し、隊員の行動に障害を招き、ひいては二次災害発生につながるので、状況に応じた判断のもとに行うとともに、隊員は必ず照明器具を携行する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |