1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 船舶火災は内部の構造が複雑で狭あいであるほか、内部に濃煙・熱気や有毒ガスが充満し、人命に対する危険が大きいので、指揮者は、船長その他の関係者と密接な連絡をとり、被災船の種別、構造、積載物や延焼状況等を把握し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な注意や指示を行う。 |
▶ 隊員が不用意に船内へ進入したため、爆風にあおられ火傷を負った。 |
2 船舶火災では、必ず防火衣・呼吸器等を着装し身体の保護を十分に行うとともに、照明器具・誘導ロープを携行し活動する。また、船舶内は機密性が高く火災時には酸欠のおそれがあるので、煙が少ない場合や鎮火後であっても、必ず呼吸器を着装して進入する。 |
▶ 船内は煙も薄く熱気もなかったので面体をはずしたところ、酸欠空気を吸って意識もうろうとなり、他の隊員に救出された。 |
3 船舶の規模・気象条件等によっては、ピッチング、ローリングにより船の動揺が激しいため、特に狭く足場の悪い場所では命綱で身体を確保するか、手すりで身体を保持するなど転倒・転落等に注意する。 |
▶ 船のローリングによりバランスを崩し転倒、右手首を捻挫した。 |
4 大型船は内部構造が複雑であり、また小型船は出入口が小さく注水により転覆等の危険があるので、退路を確保し、早期に避難できる状態で活動する。 |
|
5 タンカーの火災は、爆発や海面大火災になる危険があるので、二次災害に注意する。 |
▶ 放水中、火炎が燃料に引火、爆発して爆風により転倒して頭部を打撲した。 |
6 船舶火災は、防ぎょ活動の範囲が限定されるので、必ず周囲に声をかけ、相互に連絡を密にして破壊・放水等による危険を避ける。 |
|
7 船倉内の活動は、長時間に及ぶ場合が多いため、指揮者は隊員の疲労度を考慮し、交替要員を確保する。 |
|
8 船舶の甲板上はロープや配管、各種の突起物があり、かつすべりやすいため転倒・転落等に十分注意する。 |
▶ 甲板上で活動中、ロープに引っかかり転倒して、手足を打撲した。 |
9 放水や荷崩れによって船体が傾斜しているときは、特に足場が悪くホースも輻輳しているので、滑りや転倒に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 破壊・進入活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 斧、掛矢、とび口等の器具を使用して破壊活動を行うときは、必ず手袋を使用するとともに、破壊により開口部から一気に濃煙・熱気が噴き出すおそれがあるので、開口部の正面を避け、噴霧注水の援護を受けて行う。 |
|
2 指揮者は、あらかじめ進入目的・内部構造・火炎の状況・脱出時間・連絡方法等を隊員に指示し、進入時間と呼吸器の充てん圧力を確認させるとともに、進入隊名と人員を確実に把握する。 |
|
3 進入隊の編成は必ず複数隊員とし、命綱を結着しロープを使用して退路を確保する。 |
|
4 進入するときは、火炎の噴き出しに十分注意し、風上または風横側から進入する。 |
▶ 注水のための船窓を開放したとき、バックドラフト現象により窓から火炎が急に噴き出し顔面に火傷を負った。 |
5 船内構造は、場所によっては相当な高低差があるので、特に足場を十分確保して転落の防止を図る。 |
|
6 機関室へ進入するときは、高温のエンジン、配管等があるほか、スチームが噴出していることもあるので、熱傷あるいは呼吸器の面体・ホース等の装備の損傷に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)船窓等の破壊
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
ガラス窓を破壊するときは、上部の端から斧、とび口等を使用し、必ず手袋を着用して窓枠にガラス片を残さないよう注意する。 |
▶ ガラス窓をとび口で破壊中、手袋を着用していなかったため、ガラス片が飛散し右手を負傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 放水活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 放水を行うときは、積載物の延焼状況、船内構造等を関係者から聴取し、船体が傾斜したり、転覆しないよう噴霧注水を主体として放水量を最小限度とする。なお、船の復元力は積荷の状況・船体構造等によって異なるが、傾斜角度の限界は概ね45°であり、船内残水量及び積荷の移動等によってさらに許容角度は小さくなり、15°~20°が限界となる。 |
▶ 放水活動中、大量放水で船が傾き、隊員がバランスを失い、海中に転落し負傷した。 |
2 放水による船体の傾斜や転覆を防止するため、早期に船舶関係者等に備付けの排水ポンプの作動や可搬排水ポンプの搬送を求める。 |
|
3 船内は足場が悪いので、機関員は放水員の転倒・転落を防止するため、送水圧力をゆっくり上げる。 |
|
4 二酸化炭素による消火活動は、内部進入隊員等の全員脱出を確認してから行う。なお、出入口付近の隊員は屋外作業であってもガス漏れを考慮し、必ず呼吸器を着装する。 |
|
5 消防艇から放水砲により放水するときは、被災船で活動中の隊員の安全を図るため、相互に連絡をとり実施する。 |
|
6 タンカーに泡放射を行うときは、内圧や温度の異常上昇等で槽が破裂し、または爆発するおそれがあるので、みだりに接近せず泡放射砲や銃を使用する。 |
|
7 タンカー火災の場合は、消火後であっても可燃性ガスが残留し、照明器具用の発電機の火花等で引火することがあるので、進入するときは十分換気するとともに、必ず風上側より行う。 |
|
8 タンカーは火災の熱により、船体が膨張しリベット等の緩みや船体の亀裂等が生じ、油が流出し火面が広がることがあるので注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)甲板での放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 放水中は、ホースがずり落ちて筒先員が転倒・転落しないよう、ホースを手すり等の固定物に結着する。 |
|
2 特に甲板で放水活動を行うときは、足場が濡れて滑りやすく障害物も多いので、すべりやつまずきに注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)船室・船倉内での放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 ハッチを開放するときは、バックドラフト現象による火炎の噴き出しがあるので、ハッチの正面を避け、援護注水を受けて行う。 |
|
2 船室・船倉内での放水活動は、必ず呼吸器を着装し、命綱等により身体を確保して行う。なお、常に呼吸器の空気残量等を確認し、余裕をもって脱出する。 |
▶ 消火活動のため船室内に進入したが、命綱を使用していなかったため、緊急脱出に手間どり火傷した。 |
3 特に貨物船等において放水活動を行うときは、その積荷の積載状態の把握に努め、荷崩れによる下敷や転倒、あるいは船倉への転落に注意する。 |
▶ 船倉内で放水活動中、突然荷崩れが起こり、下敷となって足首を骨折した。 |
4 放水中は緊急の事態に備え、必ず退路を確保する。 |
|
5 旅客船は、客室の等級で個室となるなど区画が複雑で、木造の間仕切り等の可燃物が多く、フラッシュオーバー等による熱傷の危険があるので、注水態勢を整えるとともに退出路を確保する。 |
|
6 カーフェリーに積載した車両が燃えている場合は、燃料が爆発的に燃焼し、熱傷の危険があるので不用意に接近しない。 |
|
7 コンテナ船には、多種多様の積荷があるので、積荷表等で収容物を確認し、危険物、火薬類、毒・劇物や放射性物質など消火活動上危険な物品であることが判明した場合は、警戒区域を設定して全隊員に周知徹底する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)その他
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 上甲板は煙により視界が悪くなるので、周囲で活動中の隊員に注意して放水する。 |
|
|
2 はしけ(※)火災では、プロパンガスボンベが積載されている場合があるので爆発等に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
4 救助活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 救助活動のため内部に進入するときは、濃煙・熱気がない場合であっても有毒ガス、酸欠空気が滞留しているおそれがあるので、必ず呼吸器の着装等により、身体保護を十分に行うとともに、複数の隊員で進入する。 |
▷ 呼吸器の面体を着装せずに、風上から船倉内の有毒ガスを検知作業していたところ、風向きが急に変わり、ガスを吸入しそうになった。 |
2 隊員は進入前に相互に脱出時間を確認するとともに、進入後は時間の経過、空気ボンベの残量、脱出所要時間等を考慮し、無理な行動はとらない。また警報ベルが鳴ったときは、相互に連絡し直ちに脱出する。 |
|
3 船内での救助活動は、内部構造が複雑で障害物が多いので、呼吸器や誘導ロープの使用については、損傷や絡まり等に注意する。 |
|
4 大型船の内部は迷路状になっているため、原則として命綱を結着し、ロープを使用して進入する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
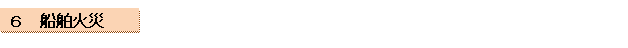
重い貨物を積んで航行するために作られている平底の船舶