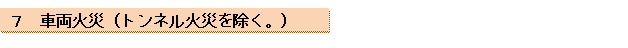1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 車両火災は、隊員と他の通行車両との接触や積載危険物等の流出、爆発による危険があるため、指揮者は早期に火災の状況・積載危険物の状況を把握し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な注意や指示を行うとともに、交通の遮断措置をとる。 |
▶ 見通しの悪い場所にもかかわらず、早期に交通規制を行わなかったため、一般車両が現場に突入して、隊員が車両と接触し、腰部を打撲した。 |
2 車両火災は、事故の衝撃等で燃料・積載危険物等の流出・引火爆発あるいは有害ガス等の発生が予想されるので、隊員は積載物品を確認するとともに慎重に行動する。 |
▶ 塩素ガス運搬車両の火災現場で消火活動中、隊員が塩素ガスを吸引して、頭痛・吐き気を訴えた。 ▶ 禁水性物質に不用意に放水したため爆発し、隊員2名が顔面を火傷した。 |
3 放置車両等の火災の場合、廃棄物などが大量に積載されている場合があるので、ドアの開放時等に積載物の落下に気をつける。 |
▶ 放置車両であったハッチバック車から出火し、車両後部の残火処理のためラゲッジルームのドアを開放した際に、満載してあったゴミと共に車両用廃棄バッテリーが崩れ落ちた際、隊員1人の右背部に落下し骨折した。 |
4 指揮者は、交通規制を実施するときは、極力警察官の早期出場を要請し、協力を求める。 |
▶ 赤旗等で交通規制を明確に指示しなかったため、通行車両と隊員が接触、右足を打撲した。 |
5 交通規制を行うときは、蛍光チョッキを着用して赤旗や誘導灯(赤灯付懐中電灯)等を活用し、他の通行車両に注意を喚起する。 |
|
6 車線を限定して車両を通行させるときは、前・後方等に監視員を配置する。 |
|
7 車両火災の現場は、事故車両からオイル等が流出し滑りやすくなっているので、転倒に気をつける。 |
▶ 現場活動中、流れ出たオイルで滑って転倒し足首を捻挫した。 |
8 夜間は足元等が暗いうえに、現場は輻輳しているので、十分周囲を明るく照らす。 |
▶ 夜間の現場活動中、ホースにつまずき、右足を捻挫した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 破壊・進入活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 フロントガラス等を破壊するときは、ガラス破片の飛散による受傷を防止するため、手袋の着用、顔面、身体の保護を行い必要以外の隊員を近づけない。 |
▶ フロントガラスを破壊中、ガラス片が飛散して他の隊員にあたり、左手甲を切創させた。 |
2 フロントガラス等を破壊するときは、斧、とび口等を使用し、正面に位置して作業をしない。 |
|
3 転覆車両はバランスが不安定であり、ずり落ちや転倒のおそれがあるので注意する。 |
|
4 トラック等は荷崩れのおそれがあるので注意する。 |
▶ 現場活動中、積荷が突然崩れ、下敷きとなって左手を骨折した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)高速道路上の活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、早期に警察・道路管理者に協力を要請する一方、事故現場の後方に赤色灯を点灯させた消防車両を停車させるとともに、非常停止板や発炎筒等を活用して、後続車両が事故現場に誤って突入するなどの二次災害を防止する。 |
▶ 高速道路で活動中、後方に対して十分な注意喚起を行っていなかったため、後続車が現場に突入し、隊員が跳ね飛ばされ右足を骨折した。 |
2 高架上で活動するときは、転落に注意する。 |
|
3 高架上の事故において、一般車道からはしごを架ていして活動するときは、てい体と他の通行車両との接触に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)軌道敷内の活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
|
1 必要に応じて、早期に鉄道関係者に送電停止と信号切り替え等による列車停止を要請するとともに、関係者の現場派遣を依頼する。 また、不意の列車の接近に備え、必ず上下線の二方向に監視員を配置する。 |
|
2 通電架線が火災の熱で切れ、垂れ下がっていることがあるので、感電に十分注意する。 |
|
3 高架上の車両火災ではしご車等を活用するときは、架てい時の架線の切断や感電に注意する。 |
▶ 列車火災の現場で活動中、隊員が切れた架線に接触し、全身に火傷を負った。 |
4 傾斜地では鉄道車両が動き出すことがあるので、鉄道関係者にブレーキ処置等を要請する。 |
|
5 軌道敷内では、枕木・砕石等でバランスを崩しやすいのでつまずきや足首の捻挫等に注意する。 |
▶ 軌道敷内の砕石に足をとられて転倒し、左ひじを骨折した。 |
6 土手や高架上で活動するときは、転落防止に配意する。 |
|
7 列車内へ進入するにあたっては、むやみに窓ガラスを破壊せず、ドアの非常開放用コックを作動させてドアを開放する。 |
▶ 窓から列車内へ進入しようとしたが、転落し腰部を打撲した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 放水活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 トラック等のタイヤが炎上しているときは、車両が傾きいて荷崩れのおそれがあるので注意する。 |
▶ 現場活動中、トラックのタイヤが焼失したため車両が傾き、積荷が崩れて隊員にあたり、右足を打撲した。 |
2 指揮者は、ガソリン、ディーゼル車、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車などの車種を見極めて、車種に応じた消火要領や注意事項を指示する。 |
|
3 燃料タンク、積載危険物等の引火爆発が予想されるときは、遮へい物を利用した泡消火活動を行う。 |
▶ 放水活動中、危険物の入ったドラム缶が誘爆し、鉄片があたり隊員3名が負傷した。 |
4 ハイブリッド車及び電気自動車に放水する場合は、少量の放水の場合感電のおそれがあるので、必要に応じて絶縁防護具などを活用する。 |
|
5 水素を燃料とした燃料電池自動車への放水の場合、水素への引火に備えて車両から距離をとり消火活動を行うこと。 |
|
6 水素を燃料とした燃料電池自動車で、水素に引火した場合、火炎を完全に消火してしまうと、未燃水素が周辺に滞留してしまい二次爆発の危険があるので、周辺への延焼阻止に努めて、水素の火炎が自然におさまるのを待つ。 |
|
7 ホース延長するときは、交通ひん繁な道路の横断を避け、万一横断させるときは、ホースブリッジを活用する。 |
▶ 道路を横断しているホースを通過車両が車体の一部に引っかけたため、職員が転倒、肋骨を骨折した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
4 救助活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 救出するときは、窓ガラスの破片を除去したり、車両の切断部の突起部を折り曲げる。 |
▶ 車両内に閉じこめられていた要救助者を救出する時、切断部の突起物に触れ、右手甲を負傷した。 |
2 要救助者を搬送するときは、他の通行車両に注意し、担架等を使用し複数の隊員で搬送するようにする。 |
▶ 要救助者を1人で抱えて搬送したため転倒し、腰を打撲した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |