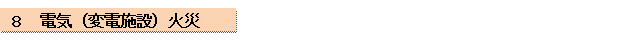1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 変電施設火災は、感電や絶縁被覆等の燃焼による有毒ガス発生、絶縁油の気化による爆発等の危険があるので、指揮者は、早期に関係者から、変電施設の構造、設備の位置、供(需)給電圧及び感電の有無等を確認し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な注意や指示を行うともに、感電危険区域を設定する。 |
|
2 指揮者は、感電事故防止のため早期に電路遮断を関係者に要請する。また、隊員は電路の遮断前はむやみに進入しない。 |
▶ 電路の遮断前に金属製の破壊器具を持って活動したため、低圧側配線に接触して感電した。 |
|
3 絶縁ゴム手袋等の防護具を使用するときは、防護具の性能とその劣下の状況を十分把握し、防護具を過信しないようにする。 なお、活動中は電流が漏えいしている可能性のある金属部分や防護具を破損するような鋭利な箇所には触れない。 |
|
4 変電施設の火災の場合は、絶縁油、配線の被覆等が燃え、多量の黒煙と有毒ガスが発生することから、施設室内に進入するときは、必ず呼吸器を着装し命綱で身体を確保する。また、進入するときは必ず複数の隊員とし、援護注水を受けて行う。 |
|
5 施設内は暗やみ、濃煙が予想されるので、十分な照明を確保するとともに、照明器具は二重に携行する。 |
▶ 照明器具を携行しないで屋内に進入したため、暗くて足元の段差に気付かず、転倒し負傷した。 |
6 施設や設備から絶縁油が漏れていることが多いので、滑らないよう足元には十分注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 破壊・進入活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 変電施設等をとび口などの器具を使用して破壊するときは、破壊箇所の正面や下方は避けるとともに、ガラスや金属片の飛散、落下による受傷を防止するため付近には隊員を近づけない。 |
|
2 破壊後の窓枠にはガラス片を残さない。 |
▶ 進入時、隊員が窓枠に残っていたガラス片に触れ、手を切創した。 |
3 施設内は構築物等の障害物があるので、進入するときや退避するときは、照明コード、誘導ロープ等に引っかからないよう注意する。 |
|
4 密閉されたキュービクル式配電箱や電気室の扉を不用意に開放すると、放電火花や絶縁油の燃焼に伴うバックドラフト現象による火炎の噴き出しの危険性があるので、ドア等の側面に位置して開放する。 |
▶ キュービクル式配電箱の火災で、不用意に扉を開放したため、放電火花で顔面を火傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)進入口の設定及び屋内進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 進入は、電源遮断後であっても放水した水に漏電しているおそれがあるので、万一に備え電気事業者や電気主任技術者等に漏えい電流を検知させ、安全を確認してから進入する。 |
|
2 エンジンカッター等の破壊器具を使用するときは、火花等に注意するとともに、作業現場付近には必要以外の隊員を近づけないようにする。 |
|
3 電線被覆には塩化ビニール等が多量に使用されていることから、その燃焼により有毒ガスが多量に発生するので、進入するときは必ず呼吸器を着装する。また、進入口付近で活動する場合にあっても、発生した有毒ガスが滞留していることがあるので呼吸器を着装する。 |
▶ 絶縁被覆を若干焼失した程度の小火現場で、呼吸器を着装せず進入したところ、のどに炎症を起こした。 |
4 施設の周囲にも、火災による有毒ガスの滞留している可能性があることに留意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)排煙口の設定
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 排煙口を設定するときは、火勢の状況を十分把握し、急激な火煙の噴き出しに備え注水態勢を整えてから行う。 |
|
2 排煙口を設定すると、急に火勢が強くなることがあるので、内部で活動している隊員とも十分な連絡をとり、排煙口を設定する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 放水活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 放水は原則として電源遮断後とし、万一通電時に放水する場合は噴霧で注水とするとともに十分な安全距離を確保して行う。 |
|
2 電源の遮断または配線の切断は、緊急やむを得ない場合を除き、電気事業関係者や電気主任技術者等に行わせる。 |
|
3 建物に放水した水が漏電経路となり、感電するおそれがあるので注意する。 |
|
4 可能な限り車両や筒先等の金属部分を接地させる。 |
|
5 キュービクル式変電設備や変電設備の火災は、扉の開放時に火炎が噴出するおそれがあるので、扉を開放するときは、側面に位置する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)屋内変電施設への放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
屋内変電施設の消火活動は、電源を遮断するまでの間は、感電を防止するため粉末消火器等で行い、延焼危険があるときは隊員を屋内から避難させ、外部壁体等へ噴霧注水を行う。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)高圧電線等への放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
|
放水活動は、噴霧注水を原則とし、十分な安全距離を保って行い、棒状注水は電源遮断後でなければ行わないようにする。 なお、万一棒状注水を行う場合は、燃焼物の真上に放水し、その落下水で消火するか、筒先を保持しないで放水台座等で固定して放水する。 |
▶ 電源遮断の前に、棒状注水をしたところ、両手に電気ショックを受けた。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)柱上トランスへの放水
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
絶縁油が燃焼しながら落下することがあるので、電柱直下の部署や通行を避ける。 |
▶ 柱上トランス火災で放水活動中、突然トランス内の絶縁油が飛び散り、顔面を火傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(5)高発泡による窒息消火
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
高発泡により消火するときは、感電するおそれがあるので施設外から行う。発泡した泡の中には、電路の遮断が確認されるまで進入しない。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
4 救助活動
共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 防火区画等により通路が複雑な場合が多いので、人命検索を能率的に行うとともに、検索の範囲を分担する。 |
|
2 人命検索は誘導ロープを設定し、退路を確保する。 |
|
3 濃煙や暗やみの中で活動するときは、照明器具を二重に携行し、通路の障害物・段差等に注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |