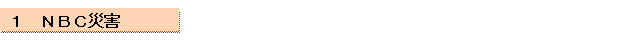§2 その他の災害防ぎょ
1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 NBC災害においては、隊員が毒劇物に触れたり、有毒ガスを吸入する危険があるので、指揮者は現場把握を十分に行い、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な注意やな指示を行う。 |
|
2 現場到着時、有毒蒸気等のガスが流出して滞留している場合があるので、消防車両は風上・風横側に部署し、危険が予測される区域には進入しないようにする。なお、隊員はむやみに漏えい現場に近づかないようにする。 |
▶ アンモニアの漏えい現場で状況の確認を待たず進入したところ、ガスを吸引し、口腔・鼻に炎症を負った。 |
3 指揮者は、毒劇物取扱責任者等の関係者から、毒劇物の種類、毒性等の性状、漏えい状況、気象条件等必要な情報を収集する。 |
|
4 有毒ガス等が発生したり、漏えいしていることを考慮し、広範囲に警戒区域を設定し、立ち入りの制限や火気の使用制限を実施するとともに、警戒区域内で活動する隊員は、必ず呼吸器を着装し、身体を防護服等で完全に被覆して活動する。なお、気象条件(風向等)の変化に十分注意して活動にあたる。 |
|
5 毒劇物の漏えい状況の検知は、毒劇物の漏えい状況が直ちに視認できず、検知実施区域内に滞留していることもあるので、呼吸器、防護服等を着装して実施する。 |
|
6 引火性のガスが漏えいしているときは、爆発等の防止のため、火花を発生するおそれのある資機材を使用しないようにする。 |
|
7 指揮者は、常に隊員の身体の変調を監視するとともに、隊員は身体の変調を感じたときは、速やかに指揮者に申し出る。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 防ぎょ活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 進入は呼吸器等を着装し、皮膚を露出させないよう完全に防護し、複数でかつ必要最小限度の人員で進入する。 |
▶ 冷凍室のアンモニアガス漏えい現場に防火衣で進入したところ、隊員の首すじが露出していたためアンモニアガスが触れ、薬傷を負った。 |
2 呼吸器等の着装は、警戒区域外の安全な場所で行う。 |
|
3 進入口の設定は、漏えい等の危険を防止するため、むやみに破壊することなく、ドア等の既設の開口部を利用し、状況により速やかに閉鎖する。 |
|
4 活動中は、他の毒劇物等の貯蔵容器に注意し、それを転倒させたり、破損させたりしないようにする。 |
|
5 毒劇物の製造所等では、地下(半地下)槽、タンク、液槽等への転落、滑落等に注意する。 |
|
6 活動後、漏えい現場から脱出するときは、除染を行った後、安全な場所に至るまで呼吸器の離脱は行わない。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)漏えい毒劇物の処理
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 有毒あるいは可燃性の漏えい蒸気・ガスを大気中に拡散させたり、噴霧注水の水に溶解させるときは、十分な広さの警戒区域を設定して行う。 |
|
2 漏えい防止及び中和作業は原則として、取扱いを熟知している毒劇物取扱責任者等の施設関係者に実施を要請する。 |
|
3 大量の水で稀釈するときは、漏えい物質を飛散させないよう噴霧注水で行うとともに十分な安全距離をとる。 |
|
4 中和するときは、十分な量の中和剤を用いて実施し、PH等を確認してから処理する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)汚染拡大の防止
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 漏えいあるいは流出している毒劇物に直接触れたり、汚染している防護具等で他の物に触れたりしない。 |
|
2 防護具等の使用資機材は、使用後指定の場所にまとめ、十分洗浄し、場合によっては廃棄する。 |
|
3 使用資機材に、放射性物質による汚染がある場合は、除染又は廃棄を関係機関に依頼する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)硫化水素災害
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、警戒区域の設定等必要な活動命令を行い、関係者や付近住民の被害の拡大防止に努めるとともに、現場における二次災害防止、隊員の体調管理等に留意する。 |
|
2 硫化水素が発生する際は、現場が高度の酸欠状態になっている可能性もあることから、現場に進入する際は呼吸器を必ず着装する。 |
|
3 事故現場の内部だけでなく、現場付近や開口部付近にも硫化水素が流出したり、滞留している可能性があるので、隊員の安全管理対策と呼吸器や防護服などで防護対策を講じる。 |
▷ 硫化水素災害で救助活動中に、ガスが再発生し、周辺の活動隊員が硫化水素ガスを吸引しそうになった。 |
4 現場に最先着した隊は、異臭がする場合には、防ぎょ態勢が整うまで扉等をむやみに開放しない。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(5)サリン災害
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
毒劇物等の品名や物性が不明な場合であって、異臭、着色ガスを確認した場合あるいは毒性ガスの存在が不明な場合であっても、現場の状況により毒性ガスが発生している可能性が高い場合又は体調等に何らかの異常が現れた場合で、警戒区域を指定したときは、適切な身体防護措置を講じて消防活動を行う。 |
|
※その他詳細行動等にあっては「化学災害(毒・劇物等)に係る消防活動マニュアル」(平成14年3月救急救助課)を参照 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(6)原子力施設等
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 放射性物質の種類、放射線の種類、強さ(測定範囲)、放射線の種類に応じた放射線測定器による放射線強度等、活動環境の把握等に努める。 |
|
2 防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、放射線測定器等を装備し放射能防護措置を講じる。 |
|
3 個人警報線量計の警報発報、放射線測定器の値が急上昇したとき等の緊急退避の対応要領を隊員に周知徹底する。 |
|
4 活動に当たっては、「被ばく線量限度」と「個人警報線量計警報設定値」を厳守する。 |
|
5 消防活動において、被ばく又は汚染のあった者は、専門家等と協議し必要に応じ健康診断を実施する。 |
|
※その他詳細行動等にあっては「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」(平成13年3月特殊災害室)「原子力施設等における対策ハンドブック」(平成16年3月特殊災害室)を参照 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(7)その他
ア 応急救護
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 応急救護所は警戒区域外の安全な場所に設置し、万一の場合に備え、解毒・中和剤、石けん、大量の洗浄用の水を準備しておく。 |
|
2 応急救護処置を行う隊員は、二次被災を防止するため、ゴム手袋等を着用する等の防護措置を行う。 |
|
3 万一、隊員が毒劇物により負傷したときは、速やかに大量の水で洗浄または解毒・中和剤により応急処置し、早急に医師の診察を受けさせる。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
イ 活動後の措置
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
活動後、各隊員は身体の異常の有無を問わず、眼、手、顔等の皮膚の露出部を十分洗浄するとともに、うがいを励行する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |