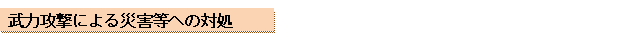§5 国民保護
1 共通事項
| 留意事項 |
|---|
1 消防本部は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、防災における体制等を参考に、市町村の国民保護部局との連携、職員の参集基準、参集した職員の活動要領、関係機関からの情報の収集体制等について整備する。 |
2 消防本部は、武力攻撃事態等が認定された場合の対応体制を整備する。 |
3 消防本部は、武力攻撃による災害(以下「武力攻撃災害」という。)やテロによる災害に対応するため、NBC対応資機材等必要な装備及び資機材の整備に努める。また消防団は、資機材や活動内容等が地域によって異なるため、武力攻撃事態等における消防本部と消防団の任務について、実情に応じた連携体制の構築を図る。 |
4 消防本部は、NBC対応資機材等を含めた消防力の整備状況について、他の消防本部と情報交換を行うなど、災害の状況に応じた相互応援体制の確立を図る。 |
5 一部事務組合、広域連合、委託等により複数の市町村を管轄する消防機関は、構成市町村における武力攻撃災害への対処等を行うとともに、当該市町村の避難実施要領で定めるところにより、避難住民の誘導を行う。 |
6 消防機関は、119番通報等を受けて、真っ先に現場での活動を実施する機関であることから、武力攻撃事態の類型ごとに、その活動時の安全の確保に関して、特に留意する。 |
7 消防団は、安全が確保されている地域において消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、情報収集、消防警戒区域の設定、消防本部の活動支援等、消防団が保有する装備、資機材等の活動能力に応じた活動を実施する。 |
8 消防長は、武力攻撃災害の対処に際し、災害の規模により自己の消防機関が保有する消防力のみでは防御できない場合や、NBC災害のように特殊な装備・資機材や専門部隊の対応が必要な場合は、平素確立した相互応援体制に基づき、市町村長を通じ、速やかに必要な応援要請を行う。 |
9 武力攻撃事態等において国民保護措置を実施する消防職団員は、特殊標章(腕章等)を着用し、身分証明書を携帯する。特殊標章(旗等)は、消防車両等の車両にも表示する。 |
10 警察等からの継続的な安全に関する情報の収集体制を確保する。 |
11 緊急連絡手段(無線機、拡声器、警笛等)とともに、緊急時における脱出手段・経路を確保する。 |
12 警戒区域内で活動する部隊の進入及び退出管理の徹底をはかる。 |
13 武力攻撃事態等が発生した際には、消火、救急及び救助などが複合した活動が想定されるほか、爆発物や毒劇物等(NBC)への対応が想定されるので、該当する活動に応じて、各章の事項をそれぞれ参考とする。 |
※その他、国民保護措置上の留意事項等については「消防機関における国民保護措置上の留意事項等について」(平成18年1月31日消防消第7号、消防災第43号、消防運第2号通知)を参照 |
2 武力攻撃事態等の認定前における対応
| 留意事項 |
|---|
1 消防機関は、武力攻撃事態等が認定されるまでの間、消防法等に基づき消防活動を実施することとなるが、多数の人を殺傷する行為等の武力攻撃災害の発生が疑われる事案が発生した場合には、119番入電時の情報や警察からの情報の収集に努め、市町村の国民保護部局へ即報するとともに、警察等との連携を密にして活動するなど消防活動の安全に特に留意する。 |
2 市町村が、当該事案へ対応するために緊急事態連絡室(仮称)を設置した場合には、当該連絡室との連絡体制を確立するなど、事態の進展を考慮した的確な対応を行う。 |
3 弾道ミサイル攻撃の場合(NBC攻撃を含む)
| 留意事項 |
|---|
1 弾頭の種類(通常弾頭であるのか、NBC弾頭であるのか。)を着弾前に特定することが困難であり、それに応じて、被害の様相が大きく異なるため、着弾後は、速やかに弾頭の種類に関する情報の入手に努めるとともに、活動に使用する装備、資機材等を適切に選択し、消防活動にあたる。 |
2 消防機関は、安全が確保された地域において、消火、要救助者の救助及び救急搬送、避難住民の誘導、災害に関する情報の収集及び提供、消防警戒区域の設定などを行うことが想定されるが、その活動要領は、通常弾頭の場合は、爆発災害に対する要領、NBC弾頭の場合は、NBC災害に対応する要領で行う。 |
3 現場における消防吏員及び消防団員の二次災害を防止するため、弾種が判明するまでの間は、常に危険の高いNBC弾頭の可能性を念頭に置いた消防活動を行う。 |
4 出動隊は、風上側からの接近、異臭の有無、人・動物の身体等への異常の有無など周辺の環境から安全の確認を行う。 |
5 弾頭の種類が不明な場合は、NBC災害対応部隊がNBC災害対応用の装備及び資機材を用いて活動を行う。(現場検知、呼吸保護器具、防護服の着用等) |
6 保有する装備、資機材等では対応不能な場合は、対応可能な装備を有する他機関等へ情報提供するとともに、市町村長を通じて都道府県知事に対し、応援部隊の出動の要請を行う。 |
7 NBC対応装備、資機材を保有していない部隊は、安全が確認できた地域において、消防警戒区域の設定、避難住民の誘導、情報収集、消火、救急搬送などの活動を行う。 |
8 現地調整所において、警察等と情報を共有するとともに、消火、救助、救急、原因物資の撤去、汚染者の除染等の活動が安全に実施されるよう調整する。 |
9 建物等の破壊状況を確認するなど二次災害の発生に注意する。 |
4 ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合
| 留意事項 |
|---|
1 突発的に被害が発生するおそれがあること、被害は比較的狭い範囲に限定される場合もあるが、ゲリラ・特殊部隊の移動や攻撃目標となる施設(原子力事業所等の生活関連等施設など)の種類によっては被害が広範囲に及ぶおそれがあること、爆発物の使用やNBCの散布などの攻撃も想定されること等の特性に留意する。 |
2 消防機関は、市町村対策本部等や警察等からの情報によりゲリラ・特殊部隊による攻撃の危険がないと判断される地域において、避難住民の誘導、緊急通報の住民への伝達、消火、要救助者の救出及び救急搬送、消防警戒区域の設定、生活関連等施設の安全確保に関する支援などを行うことが想定される。 |
3 活動現場に所在する警察等と緊急連絡体制を確保したうえで活動を行う。 |
4 国から提供される安全に関する情報を迅速に受領するため、市町村対策本部との緊急連絡体制を確保する。 |
5 着上陸侵攻・航空攻撃の場合
| 留意事項 |
|---|
1 着上陸侵攻や航空攻撃の場合は、その兆候を察知することは比較的容易と考えられるが、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲にわたるとともに、期間が比較的長期に及ぶことが想定されるという特性に留意する。 |
2 着上陸侵攻や航空攻撃の場合は、その時点で示されることとなる国の対処基本方針やそれに基づく総合調整、都道府県及び市町村対策本部の方針を踏まえ、消防機関は、安全が確保された地域において、避難住民の誘導等の必要な国民保護措置を行う。 |
6 緊急対処事態における災害への対処
| 留意事項 |
|---|
緊急対処事態における災害への対処については、原則として、武力攻撃災害への対処に準じて行う。 |