1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 風水害は、土砂の崩壊、増水等による二次災害の危険があるので、指揮者は災害の状況、気象条件(※)、地形等(土砂災害警戒区域等)の消防活動上必要な情報を収集し、現場を十分把握するとともに、活動の安全を確保するため、速やかに全隊員に対して具体的な注意や指示を行う。 |
▶ 土砂崩壊の災害現場において、豪雨の中生き埋めになった団員の救出作業中、再び崩壊があり、救出作業に従事し、または国道上に待機していた消防団員らが犠牲となった。 |
2 指揮者は常に隊員の行動を掌握するとともに、災害状況に応じて、監視員や消防部隊を指定して、重点的な安全管理体制を確立し、二次災害を防止する。また、隊員は単独行動を絶対に行わない。 |
▶ 人命検索中、崩壊場所が再度崩れ、隊員1名が下半身土砂に埋まり、足を骨折した。 |
3 土砂災害は、雨がやんでからもしばらくは、拡大したり、同じ場所で再び発生することがある。特に土石流は複数回発生する傾向があることに留意する。 |
|
4 指揮者と監視員は崖崩れ等の前兆現象に十分注意するとともに、前兆現象を覚知したときは隊員の避難等適切な措置を講じる。また、作業中の隊員が覚知したときは、速やかに指揮者に報告する。 |
|
5 指揮者は、消防活動が長時間にわたるときは、疲労による注意力の散漫に起因する事故を防止するため、隊員を随時交代させるとともに、活動しない隊員は安全な場所で待機させる。 |
▶ 浸水場所で活動中、疲労から足をとられて転倒、杭で頭を打ち、右側頭部を切創した。 |
6 災害現場で多数の資器材や大型機械を使って作業するときは、危険を伴うので、平素から資器材の保守管理を適正に行うとともに、隊員相互の距離を保ち、周囲の安全を十分確認しながら作業を行う。 |
▶ 杭打ち作業中、掛矢の頭部が割れて破片が飛び、隊員の目にあたり負傷した。 ▶ 土砂の排除作業中、スコップが横の隊員にあたり、右手を切創した。 |
7 風水害の現場では気象的悪条件下で作業するため、状況に応じ防火衣でなく、雨合羽、救命胴衣、安全帯の着装に配慮するとともに、資機材として、携帯拡声器、携帯無線機、強力ライト、鋸、スコップ、とび口、救助ロープを携行するなど作業に適した装備で行う。特に、夜間の作業には、足場等の安全確保のため作業範囲全体を十分に明るく照らす。 |
▶ 夜間の作業中、照明が不十分なため、材木から出ていた釘を踏み抜き、足を負傷した。 |
8 隊員は、携帯拡声器、携帯無線機、強力ライト等の携行を相互に確認する。 |
|
9 浸水地域では、とび口や計測棒等により水の深さを確認しながら行動し、水中の障害物や小河川、溝等の危険箇所には、旗・ロープ等で標示する。 |
▶ 浸水箇所を調査中、U字溝に足をとられ左足首を捻挫した。 |
10 指揮者は、安全確認・安全監視等の安全管理のほか、退避エリア・退避経路の確保、救助・避難誘導要領等救助活動の実施要領等に関する活動方針を全隊員に徹底するとともに、異常現象が発生した場合の伝達方法や安全管理を行う隊員間の役割分担を決定し全隊員に周知する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 防ぎょ活動
(1)警戒
ア 河川の警戒
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 増水状況等を把握するときは、突風や濁って河川に転落するおそれがあるので、固定物に命綱を結着する。 |
▶ 河川の増水状況を巡回調査中、突風により堤防の天ばより転落し、腰部を打撲した。 |
2 堤防の決壊等事態の急変に備え、常に退路を念頭に置きながら巡回する。 |
|
3 積土のう等で補強してある箇所に近づくときは、崩壊の危険性が高いので十分注意する。 |
|
4 河川から道路に水があふれ、河川と道路の境界が視認できないときは、河川へ転落するおそれがあるので十分注意する。 |
▶ 非番に台風の接近に伴う非常招集を受けて消防本部参集時に河川に転落し死亡した。 |
5 車両で警戒するときは、風雨により視界が狭く、路面が悪い条件となるので周囲に注意し、慎重に行動する。 |
|
6 警戒等により河川に近づくときは、急激な河川の増水に注意し、増水等の異変を察知したら、直ちに避難する。 |
▶ 河川で検索活動中の隊員が、急激な河川の増水により、流され死亡した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
イ 浸水地域の警戒
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 浸水により危険物や毒劇物等が流出することがあるので、特に工場や研究機関等の周囲では、水の色・臭気に気をつける。 |
|
2 浸水箇所の水深が浅い場合であっても、急激に増水することがあるので十分注意する。 |
|
3 マンホールの吹き出しによる受傷危険や、マンホール蓋の移動による転落危険があるので十分注意する。 |
|
4 道路の陥没や路肩の崩れ等も考えられるので、これらに配意した車両走行を行う。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
ウ 土砂災害時の警戒
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 崖崩れ危険箇所では、崖からの土石の落下、擁壁のふくらみ・亀裂、排水施設の崩壊など状態を確認する。また、崖崩れに巻き込まれないよう危険箇所の真下には位置しない。 |
|
2 崖下の道路の通行は努めて避け、やむを得ず通過するときは、落石、崩壊等に十分注意する。 |
▶ 崖崩れ危険区域を巡回警戒中、落石により右足を打撲した。 |
|
3 崖崩れ等の現場で水防活動を実施するときは、次の現象が現われたら二次災害発生のおそれがあるので注意する。
|
▶ 崖から大量に噴き出していた湧水が急に止まった後、大規模な崖崩れがおこり消防団員等が多数犠牲となった。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
エ 強風時の警戒
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 風による瓦や看板等の落下・飛散等に注意する。 |
▶ 商店街を巡回中、落下してきた看板で右肩部を打撲した。 |
2 切り通しやずい道の出入口は、突風が起りやすいので飛散物等に注意する。 |
▶ 車両で巡回中、切り通しに差しかかったところ、飛んで来た木片が車のフロントガラスにあたり、ガラスが飛散し、隊員2名が顔面を切創した。 |
3 電柱等が傾斜したり倒れているときは、垂下している電線に接触し、感電するおそれがあるので注意する。 |
|
4 歩行困難な強風(突風)の場合は姿勢を低くし、固定物につかまるか、遮へい物を利用して身体の安全を確保する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)資機材の搬送
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 資機材を搬送するときは、足元に注意する。特に、重量物や大量の資材の場合には可能な限り、動力機械器具等を活用する。 |
▶ 土俵を搬送中、バランスを崩して転倒し、足首を捻挫した。 |
2 強風時に表面積の大きい物を搬送するときは、風圧による転倒や搬送物の落下等に気を付ける。 |
▶ ゴムボートを車両に積載中、強風のためボートごと地面に転落し、右足首を捻挫した。 |
3 多人数で担いで搬送するときは、指揮者の号令により歩調を合わせて行う。 |
|
4 車両により資機材を搬送するときは、シートやロープで固定して落下を防止する。 |
|
5 資機材を携行する場合には、安全確保を図るため可能な限り両手をふさがない搬送方法とする。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)水防工法の実施
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 活動時は、救命胴衣や命綱を着用する。 |
|
2 土のう等重量物の持ち上げは、腰を低くして背筋を伸ばし、膝の屈伸を活用した姿勢で行う。 |
|
3 作業開始前に流木、倒壊家屋、崩壊のおそれのある土砂等を除去する。 |
|
4 足場を整えて、無理な姿勢での作業は行わない。 |
|
5 掛矢やスコップ等の資機材を使用するときは、他の隊員と接触しないよう注意する。 |
▶ 掛矢で杭打ち作業中、打ち損じて杭を支えていた隊員にあて、腕を負傷させた。 |
6 杭打ち作業をするときは、掛矢を確実に保持するとともに、打ち損じないよう注意するとともに周囲の人を近づけない。 |
|
|
7 堤防上で水防活動を実施するときは、次の前兆現象が現われたら、破堤のおそれがあるので注意する。
|
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
3 救助活動
(1)共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 二次災害を防止するため、崩壊のおそれのある土砂、落石を排除する等、隊員の安全確保を図る。また、確保ロープの使用が安全確保を図るために必要と考える場合は、状況に応じて活用する。 |
|
2 活動現場全体を見通すことができる場所に監視員を配置する。 |
|
3 万一に備え、緊急避難の方向や合図等を全員に周知徹底する。 |
|
4 危険を察知したときは、即刻避難する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)ボートによる救助
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 流速のある場所ではボートの操作が困難であるので、ロープを展張し、ボートが流されないようにする。 |
|
2 ボートへの乗降は一人ずつ順序よく行い、転覆に気を付けるとともに、とび口やロープ等によりボートを固定する。 |
|
3 要救助者を艇上に収容するときは、ボートの定員に留意するとともに、不安定な姿勢で不用意に手を差し伸べると、救助者も引き込まれ水中に転落するおそれがあるので、重心を低くして引き上げる。 |
|
4 ボートでの救助は、風上と上流からの救出を原則とする。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)救命索発射銃及びロープ等による救助
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 救命索発射銃の取扱いは、危険が伴うので、発射するときは他の隊員を近づけない。 |
|
2 救命索発射銃を発射するときは、目標付近の安全を確認するとともに、警笛や拡声器等で隊員等に合図する。 |
|
3 展張ロープは、作業に応じた十分な強度があるものを使用する。 |
|
4 スローバッグやヒービングラインを投げるときは、状況に応じて命綱で身体を確保し、足場等に注意して行う。 |
▶ 艇上でヒービングラインを回転中、ボートが揺れたため、バランスを崩して転倒し、右腕を骨折した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)土砂災害時における救助
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
|
1 消防力が劣勢の場合 短時間に特定の地域において多数の救助事案が発生するような大規模な土砂災害では、消防力が劣勢の中での救助活動を余儀なくされる。この段階には二次災害に危険性が極めて高い環境下であるため、次の事項に十分留意して可能な限りの安全確保を図ったうえで救助活動を行う。
|
|
|
2 複数の消防部隊で活動する場合 複数の消防部隊で活動する場合は、前記1に記載のほか、以下の事項に留意し活動する。 なお、前記1の消防力が劣勢の場合においても、可能な限り下記の事項を行う。
|
|
|
3 関係機関集結後 各関係機関(※) が集結後の安全管理は、関係機関ごとの専門分野に応じた適切な役割分担を行い、合同調整所(現地合同指揮所)等において調整のうえ、有機的な連携のもと一体的に行うよう働きかける。
※ 各関係機関
都道府県等土木事務所(施設管理者)・国土交通省(緊急災害対策派遣隊〔TEC-FORCE〕)、消防研究センターなど |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
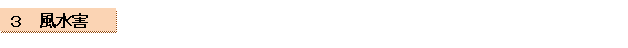
気象警戒・注意報、雨量観測情報、土砂災害警戒情報等の気象に関する情報