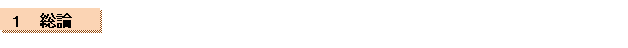§3 事故等に伴う救助活動
1 共通事項
(1)資機材の選定及び搬送
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 資機材は、使用目的や強度を考慮して選定するとともに、使用限界を超えた使い方をしない。 |
▶ 交通事故現場で、押し込まれた車両前部を引っ張るため、ロープを使用し、消防車両でけん引を始めたところ、ロープが金属角部に触れたため切れ、跳ね飛んだロープ端で顔面を強打した。 |
2 資機材の搬送は必要な人員を確保し、指揮者の指示のもとに足元に注意しながら実施する。特に、重量物については、歩調を合わせて搬送する。 |
▶ 油圧式救助器具を搬送する際、取手を保持していなかったため、手がはずれ足の甲へ落とし負傷した。 |
3 資機材を使用する場合は、車両から降ろした時点で作業点検を行った後、災害現場に搬送するとともに、各資機材の取扱い方法を習熟する。 |
▶ 大型油圧スプレッダーをドアの付け根部分と運転席左側面に先端チップを設定。開放後、当スプレッダーを車外に搬出する際、スプレッダー閉鎖時に左手の指をチップ部分に挟まれ負傷した。 |
4 現場で調達した資機材を活用する場合は、資機材の性能や強度等を把握したうえで使用するともに、必要に応じて専門家に助言指導を求める。 |
|
5 支点や支持物は、必ず強度を事前に確認した後に使用する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)救出活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、災害の状況、天候の変化、地形等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動の中断、縮小等の必要な措置を講じる。 |
|
2 指揮者は、活動スペースの確保、資機材の選定、隊員の経験・能力や体調等を考慮した任務分担の指示等、活動環境の安全確保体制を図る。 |
|
3 災害に応じた個人装備の完全着装を行うとともに、常に二次災害危険を予測して活動する。 |
|
4 出血のある傷者を扱う場合は、事前に感染防止措置を行った後に活動する。 |
|
5 危険な状況変化を察知したときは、一時退避するとともに指揮者に報告する。 |
|
6 活動は、努めて二重の安全措置を考慮する。 |
|
7 状況や下命内容等が不明確なときは、活動を安易に開始・継続しない。 |
|
8 迅速性のみにとらわれず、安全・確実な活動を優先する。 |
|
9 救出にあたっては、関係者から早期に救助活動に必要な情報を収集し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な注意や指示を行う。 |
▶ 進入後、命綱をはずし、単独で行動中、方向感覚を失い、あわてて脱出口を求めているうち、転倒し、手足を負傷した。 |
10 救助隊の編成は複数隊員とし、指揮者は常に隊員の把握に努め単独行動をさせない。 |
|
11 指揮者は、活動隊員の体調変化や疲労状況等を把握するとともに、事故防止のため隊員の注意を喚起する。 |
|
12 隊員の疲労を考慮し、必要により交替要員を確保する。 |
|
13 指揮者は、救出活動中に状況の変化が生じたときは、隊員に対し速やかに具体的な措置を指示する。 |
|
14 隊員は、救出活動中必要に応じて相互に声をかけ合い、相互に連携を図るともに、安全を確認する。 |
|
15 救出のため進入するときは、周囲の状況に配意しながら脱出経路を確保する。 |
|
16 高所に進入するときや高所作業を行うときは、命綱や他隊員による確保等により転落防止を図る。 |
|
17 火災、有毒ガスの発生、崩壊等二次災害が予測されるときは、警戒区域を設定する。 |
|
18 夜間や暗い場所等で活動するときは、十分照明を確保し、周囲の障害物に注意する。 |
|
19 救助活動と安全の確保に必要な範囲に警戒区域を設定し、ロープ等により明示する。また、必要により警戒要員を配置する。 |
|
20 道路や軌道敷内で、後続車両・通過車両等による追突・接触事故に巻き込まれるおそれが予測されるときは、警戒要員を配置する。 |
|
21 落下物、転落、倒壊危険等が予測されるときは、活動隊員の進入禁止区域をロープ等で設定し、監視員を配置する。 |
|
22 感電する危険があるときは、活動隊員に周知し関係者に電路の遮断を要請する。 |
|
23 交通事故等で出火危険が予測されるときは、消火器や放水準備等の消火手段を確保する。 |
|
24 付近住民や関係者等の危険が予測されるときは、安全な場所に避難誘導を行う。 |
|
25 山岳における救出活動は、足場が不安定で地形が複雑に入り組んでいるので、谷等に転落しないよう必要に応じて身体を確保する。 |
▶ 山岳における行方不明者の捜索活動中に職員1名が谷に滑落し死亡した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)担架による搬送活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 要救助者を担架に収容するときや担架を持ち上げるときは、腰椎損傷を防止するため、全員が十分に腰を落とし、呼吸を合わせる。 |
▶ 負傷者を担架に乗せて持ち上げる際、隊員同士のタイミングが合わず、一方の隊員に負荷がかかり、腰椎捻挫をおこした。 |
2 階段等で担架を搬送するときは、担架前部と後部の隊員間で声をかけ合い、歩調を合わせ、つまずき等の防止を図る。なお、必要に応じて誘導員を配置する。 |
|
3 狭い場所で担架搬送を行うときは、壁体あるいは手すりと担架の間に手を挟まれないよう注意する。 |
▶ 負傷者を搬送するため階段を降りる際、無理な姿勢となったため転倒し、ひざを負傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(4)撤収、引揚げ
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 指揮者は、活動後の隊員の体調変化や疲労状況等を把握するとともに、撤収時における事故防止のため隊員の注意を喚起する。 |
|
2 資機材を搬送するときは、隊員は自ら確認呼称を行うとともに、相互に声をかけ合い資機材の収納を行う。 |
▶ 救出完了と同時に気が緩んで、エアソーを手渡すとき、確認呼称を怠り、足の甲に落とし負傷した。 |
3 資機材は、数量や機能等異状の有無を点検し、事後に備える。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 積雪・凍結時の留意事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 厳寒時にあっては、手足等の感覚が麻痺し、体力が平常時よりも低下するので、確保は複数で行う。 |
|
2 雪上での確保は極力避け、必要なときは足がかりのある場所で座り確保で行う。 |
|
3 資機材は機能の低下を防止するため、布やシート等の上に置くこととし、不用意に雪の上に置かない。 |
|
4 斧やハンマー等の使用時は、雪が付着すると、滑って手から外れる危険があるので注意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |