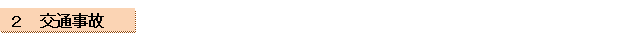1 破壊・進入活動
(1)ドア、窓枠等の破壊
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 破壊・進入活動を行うときは、他の交通に十分注意し、二次災害の防止を図る。 |
|
2 事故車両に車輪止めを施し、車両の停止措置を行う。 |
|
3 事故車両の燃料漏えいがある場合は、事故車両の電源を遮断し、火花の発生する器具の使用を避けるとともに、消火態勢を整えておく。 |
|
4 事故車両の切断等を行うときは、ワイヤロープ、ロープ、ウインチ等を用いて事故車両の横転・転落、積み荷の荷崩れ等の防止を図る。 |
▶ 横転したトラックの積荷が、活動中の隊員に落下し、肩を打撲した。 |
5 破壊器具を操作するときは、定められた姿勢をとり、足場を安定させるとともに、滑りまたは外れに注意して確実に保持する。 |
▶ 金てこでドアをこじあけようとはずみをつけて押したところ、金てこがはずれて勢いあまって手を車体に打ちつけ、指を骨折した。 |
6 路面上に漏えいした油があるときや降雨時などは、滑りや転倒に注意する。 |
|
7 車両上の不安定な箇所での活動には、必要により身体の確保を行う。 |
|
8 ハイブリッド車や電気自動車が事故対象の場合は、駆動用電池、配線等へ触れないようにする。また、事故車両から液体の漏れ等がある場合は、駆動用電池の電解液による危険性もあるので安易に触れない。 |
|
9 高速道路上での事故発生時の場合、一般車両の通行は、二次災害を防止するため、警察や関係機関に要請し、交通規制を早期に実施する。 |
▶ 乗用車のスリップ事故に際し、後続の冷凍車が現場に駐車中のパトカーに衝突、横転し、その下敷きとなり死亡した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)事故車両への進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 進入口にガラス片や金属片等の鋭利な突起があるときは、折り曲げたり、当て布等の措置を行う。 |
▶ 車輪がはずれて不安定になっている車両の中から救出するため、隊員が車内へ身を入れたところ車体が傾き、よろめいて窓枠に残っていたガラス片に接触して肩を負傷した。 |
2 事故車両がハイブリッド車や電気自動車の場合は、短絡及び感電のおそれがあるため、帯電手袋を着用した上で、サービスプラグ等を取り外し、高電圧回路を遮断した後、救助活動を実施する。 |
|
3 水素エンジン車の場合は、水素漏れのおそれがあるので、水素漏れの音がする場合は安易に近付かない。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(3)低所への進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 谷や崖下等へ進入するときは、傾斜の緩い場所や落石・崩壊の危険度の少ない場所を選定するとともに、電柱や立木等を利用し固定ロープを設定する。なお、資機材は原則として吊り下ろす。 |
|
2 指揮者は、落石や崩壊等に備えるため、監視員を配置するとともに、隊員は足元に注意し、落石や崩壊が起きないよう慎重に行動する。また、落石、崩壊その他落下物等を発見した者は、直ちに大声で他の隊員に知らせる。 |
▶ 夜間、エンジンカッターと投光器を両手に下げて土手下の現場へ降下する時、途中で足をすべらせて、転倒し、エンジンカッターで腕と肩を強打した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 救出活動
(1)人力による救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
事故車両の一部を持ち上げて要救助者を救出するときは、隊員全員が十分に腰を下ろして、呼吸を合わせて行い、腰部の負傷や手足をはさまれないよう注意する。 |
▶ 中腰のまま要救助者を抱きかかえたため、腰部を負傷した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)資機材による救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 要救助者を救出するため、資機材を使用して事故車両の引き上げや引き下ろし等を行うときは、手足を挟まれないよう注意する。 |
|
2 樹木や電柱その他の工作物等を牽引支持物等として使用する場合は,事前に強度を十分確認してから行う。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |