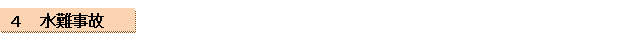1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 水難救助は、水中という特殊な環境下で広範囲に、しかも長時間にわたり活動し、危険を伴うものであるので、指揮者は水難事故現場の状況等を十分把握し、隊員の活動の安全を確保するため必要な措置を講じる。 |
|
2 指揮者は、水難救助にあたる隊員の活動状況を把握するため、監視員を配置する。特に、潜水等を行うときは、隊員の活動状況の把握が困難となるので、水上にも監視員を置く。 |
|
3 指揮者は、隊員の身体の変調や疲労の状況を把握するとともに、必要に応じて交替要員を確保しておく。 |
|
4 油の流出及び水質の汚染等が予測される場合は、ドライスーツと感染防止手袋等の活用を図る。 |
|
5 河川の水門等で、狭あいな場所や活動困難な場所にある場合は身体を命綱等で確保し、転落防止を図る。 |
▶ 農業用水水門の隙間に挟まれた要救助者を救出しようとしたところ、当人も挟まり、30分後に救出され入院加療するが死亡した。 |
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 救出活動
(1)陸地からの救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 隊員は、足元の滑りや堤防などの崩壊により水中に転落しないように注意する。 |
|
2 隊員は、要救助者に水中に引き込まれないようロープ等により身体を確保する。 |
▶ 護岸上で両ひざをつき、片手を差し伸べて助けようとしたが、要救助者の力が強く、水中に引っ張り込まれ転落した。 |
3 海岸沿いでの救出は、高波にさらわれる等の二次災害を防止するため、必要に応じて活動場所を移動する。 |
▶ 釣り人が荒波に転落した際に、一旦岩場に引き上げたが、傷病者を観察しているところに高波が打ち寄せ海中に落下し死亡した。 |
4 はしご、クレーン車等による救助に際し、足場の良い場所を選定し、転倒防止に十分配意する。 |
|
5 活動にあっては、救命胴衣を着装する。 |
|
6 夜間は照明により安全の確保を十分行い活動する。 |
|
7 橋上での救助活動は、一般車両の走行に注意を払い活動スペースを確保する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)水中での救出
ア 泳ぎによる救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 隊員は泳力があり、体調の良好な者の中から指定する。 |
▶ 池で溺れている少年を救助しようと、救急隊長が池に飛び込み水難救助活動中に溺れて死亡した。 |
2 着衣のままいきなり飛び込むと、着衣が水を含んで動きがとりにくくなるので、脱衣して、足から入水する。 |
|
3 水中で救出するときは、命綱等で身体を確保する。なお、流れのある場合は、救命胴衣を使用する。 |
|
|
4 要救助者へ接近するときは、抱きつかれないよう背後から行う。 なお、抱きつかれたときは、水中に身を沈めてかわす。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
イ 舟艇による救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 流れのある場所では、操艇が困難であるのでロープを展張し、舟艇が流されないよう注意する。 |
|
2 乗艇員は、万一の転覆等に備え救命胴衣を着用する。 |
|
3 乗艇員は、転覆防止のため定員以下とし、常に舟艇のバランスを失わせないよう注意する。 |
|
4 舟艇による救出は、原則として艇尾から引上げ、重心の移動に注意する。 |
|
5 要救助者を舟艇に収容する際は、不用意に手を差し伸べると、救助者も水中に転落するおそれがあるので、重心を低くして引き上げる。 |
|
6 夜間に舟艇等を使用する場合、灯火を使用し位置を明確にする。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
ウ 素潜りによる救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 素潜りは流れのない場所を原則とする。 |
▶ 流れのある場所で、素潜りを強行したところ、疲労から水中での身体コントロールを失い、流されて同僚に助けられた。 |
2 潜水は余裕をもって行い、無理な潜水はしない。 |
|
3 水深を把握し、経験のある潜水深度以上には潜水しない。 |
|
4 水面には浮環・救命胴衣など浮力が大きく、つかまりやすい物を配置し、浮上時の休息用に使用する。 |
|
5 水上監視員は潜水開始時分を確認し、浮上時分を予測して、異状の早期把握に努める。 |
|
6 潜水者は、潜降中耳抜きがうまくできないときは、いったん浮上し、水上監視員にその旨を告げるとともに、状況により指揮者に交代等を申し出る。 |
▶ 水深4メートルの湖底へ向かっている時、耳抜きがうまくいかなかったのに、そのまま湖底まで行ったところ、耳内(鼓膜)痛と鼻出血を負った。 |
7 潜水にあたっては、杭等の水中障害物に身体を拘束されないよう注意する。 |
|
8 上陸後は、水質に応じて目・口をはじめ身体の洗浄や消毒を行う。 |
|
9 活動後は、暖を採り、保温と休息に努める。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
エ 潜水器具を使用した救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 労働安全衛生法や高気圧作業安全衛生規則の定めを遵守する。 |
|
2 水中では、陸上に比べて生理的負担が極めて大きくなり、鼻や耳に障害が現われるばかりでなく、肺に重大な障害が生じるおそれもあることから、体調を確認し良好な隊員以外は潜水させない。 |
▶ 風邪気味であった隊員を人員の都合と、水深が5メートル前後と比較的浅い場所ということで、あえて潜水させたところ、その隊員が約3メートル潜降した時、耳抜きが不調となって、痛みを感じ、鼻出血した。 |
3 水深、水流、潮の干満、水中障害物等の状況を把握し、これらに応じて、アンカー、潜水場所水上標識(旗)、水中昇降索、命綱等の安全対策を講じる。 |
|
|
4 水上監視員は次の事項に留意し、安全の確保に努める。
|
|
5 潜水はバディを基本とした複数によることとし、検索ロープを活用するなど協力して安全を確保する。 |
|
6 水中での絡み等を防ぐため、針金、索、杭等の間を不用意に通り抜けない。なお、水没船や水没車両等へは原則として進入しない。 |
|
7 潜水中に水中障害物に拘束され、やむを得ず命綱等をはずした場合において、バディの相手を見失ったり、連絡が途絶えたりしたときは、相手方の呼吸音や信号音を聞くとともに、自らも金属等をたたいて信号を送り、それでも不明な場合は直ちに浮上して異状を報告する。 |
|
8 潜水中に身体や装備に異状を感じたときは、相手方に伝え、浮上して報告する。 |
|
9 常にバディは相互に空気ボンベの残圧を確認し、空気圧の低い者を基準に行動する。 |
|
|
10 浮上するときは、肺破裂を防止するため次の事項に留意する。
|
|
11 障害物への衝突や接触を避けるため、両手または片手を上に伸ばし、上を見ながら浮上する。 |
|
12 けいれんその他の理由により、自力での浮上ができないなどの緊急の場合には、バディの相手方に伝え、救援を受けるか、または救命胴衣をふくらませて浮上する。なお、救命胴衣を使用して、自力で浮上するときは、浮上速度が速まり、肺破裂のおそれがあるので、呼気は意識して吐き出すようにする。 |
|
13 活動後は、水質に応じて、目・口をはじめ身体の洗浄と消毒を行う。 |
|
14 活動後は、暖を採り、保温と休息に努める。なお、水深10m以上での潜水後は、体内ガス圧減の法定休息時分を遵守する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
オ 急流河川での救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 上流・下流にそれぞれ上流監視警戒隊、下流活動隊等の監視員、バックアップ隊員を配置し、警戒・支援活動にあたる。 |
▷ 増水した河川で、要救助者を救出中、急流に巻き込まれ溺れそうになった。 |
2 ウエイトの装着は厳禁とする。 |
|
3 身体に直接命綱等を結着すると、急流では水中に引き込まれたり、腹部が締め付けられ呼吸ができなくなるため、絶対に身体に直接命綱等を結着しない。 |
|
4 長時間活動に伴う低体温症などに配慮するとともに、隊員の体調管理を行う。 |
|
5 急流河川の音により、指示や命令等の伝達障害が発生する場合があるので、拡声器等を活用する。 |
|
6 夜間での活動は、照明器具を十分活用し、活動に必要な明るさを確保するとともに、原則として水中の捜索は行わずに、陸上からの救出手段を優先して実施する。 |
|
7 ボートによる救助において、要救助者を引き上げる場合は、転覆に留意する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |