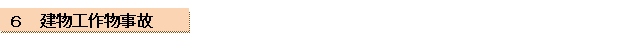1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 建物工作物事故の状況は様々であるので、指揮者は関係者から事情を聴取して、事故現場の状況等を把握し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な注意や指示を行う。 |
|
2 エレベーター等が不意に作動したり、あるいは隊員が感電しないようにするため、活動開始前に電源を確実に遮断し、スイッチ部には監視員を配置する。 |
|
3 高所作業等を行う場合は、活動隊員の二次災害の防止措置を講じる。 |
|
4 地下や階段が暗い場合は、進入時に転倒・転落危険があるので、投光器等を活用したりとび口等で足元を確認しながら進入する。 |
|
5 倒壊による現場は、トタン・ガラスや鉄筋等鋭利な物による受傷危険があるので、毛布等による被覆、危険物品の除去、折り曲げ等により危険を排除して活動する。 |
|
6 トタン等を剥がす時は、ぬれた革手袋を使用して引き離そうとすると切創危険があるのでとび口を活用する。 |
|
7 釘や針金による踏み抜き防止のため、安全措置が施された編上靴等を着用する。 |
|
8 粉じん等によって目や呼吸器系の受傷を防止するため、防塵メガネと防じんマスクを使用する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 救出活動
(1)閉じ込められ、はさまれ等からの救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 エレベーター等に進入するときは、制限荷重オーバーにならないようにする。 |
|
2 エレベーターの昇降路への転落防止のため救出活動に関係のない昇降路扉の開放を禁止する。状況により監視員を配置する。 |
|
3 エレベーター等の床と、階床との間に間げきがある場合は、昇降路内へ落ち込まないよう慎重に行動する。 |
▶ エレベーター天井の救出口(非常口)から進入する意図で、不用意にエレベーター屋根部へとびおりたところ、付着していた油やほこり等ですべって転倒し、腰部を強打した。 |
|
4 エレベーター天井の救出口から進入するときは、次の事項に注意する。なお、この方法は昇降路への転落の危険があるので極力避ける。
|
|
5 建物内等では、火花を発生する切断器具等の使用は、努めて避ける。 |
|
6 エンジンカッター等の火花を発する資機材を使用し破壊するときは、傷病者保護、可燃物の除去、消火態勢の整備など出火防止の措置を講じる。 |
|
7 マンションの個室等に閉じ込められた者を救出するため、ドア等を破壊するときは、破壊片の飛散等に注意する。 |
▶ ガラス戸を開放できなかったため、ガラス戸を一部破壊したところ、ガラス片が飛散し、手を切創した。 |
8 窓から救出するときは、窓枠や手すり等の強度を確認し、不用意に手をかけたり、足をかけたりしない。また、窓ガラス・障子等ははずして作業スペースを広くすることも考慮する。 |
|
9 窓外へ身を乗り出して救出作業をするときは、他の隊員の確保を受けるか、命綱をつけるなどして転落防止を図る。 |
|
10 要救助者を高所からロープで吊り下げて救出するときは、救助ロープの確保は、背筋を伸ばして、安定した姿勢をとり、肩または腰確保による操作によって、要救助者の体重を支え、コントロールする。なお、余長ロープは、つまずき、足の絡み等により転倒の原因ともなるので注意する。 |
|
|
11 はしご車を利用して高所から救出するときは、転落防止やタイミングのずれによる不慮の事故を防止するため、次の事項に留意する。
|
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)下敷き事故からの救出
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
家屋・塀の倒壊や荷崩れのおそれがあるときは、ワイヤロープやロープ等で固定する等の措置を講じる。その際、わずかな振動で倒壊することがあるので、慎重に行う。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |