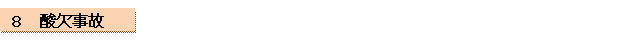1 共通事項
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 酸欠事故の状況は様々であるので、指揮者は、関係者から事情を聴取して、事故現場の状況等を把握し、活動の安全を確保するため、速やかに隊員に対して具体的な注意や指示を行う。 |
|
2 酸欠事故現場で活動するときは、必ず呼吸器を完全に着装し、必要に応じて身体の確保等を行う。酸欠ガス現場と予想されるマンホール、古井戸等は、呼吸器を着装しなければのぞき込まない。 |
|
3 身体の露出部分をなくし活動を行う。 |
|
4 警戒区域を早期に設定し、活動隊員以外の進入禁止措置を講ずる。 |
|
5 ガス関係者と連携し、危険を排除しながら救助活動を行う。 |
|
6 ガス漏えい現場では、防爆型の資機材を使用する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
2 救出活動
(1)地下室、地下槽等への進入
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 早期にガスの種別と酸素濃度等を測定し、隊員にガスの性状や危険性等の周知を行う。 |
|
2 酸欠ガスの測定はマンホールの周囲から中心へと測定し、酸欠箇所を特定する。 |
|
3 酸素欠乏空気、窒素ガス、メタンガス等無色無臭であるガス等も少なくないので、臭覚等の感覚による認知には頼らない。また噴き出している場合もあるので、不用意な進入やピット・槽内ののぞき込みはしない。 |
▶ 浄化槽の酸欠事故現場で救助に駆け付けた隊員が呼吸器の面体をつけずに不用意に進入したため、硫化水素ガスを吸って倒れた。 |
|
4 進入口に入口統制者を配置する。入口統制者は次の事項に留意し、安全の確保に努める。
|
▷ 入口統制者が、ロープ確保等を怠ったため、隊員用ロープ、救出ロープ、器材吊下げロープ等の区分けが不明になり、隊員が脱出するのに時間がかかり、危うく人身事故が発生するところであった。 |
5 坑内等は酸欠に加え、暗く温度の変化も大きいなど悪条件のため、適性と技量等を十分考慮し活動隊員を指名する。 |
|
6 進入隊員の心理的状態を把握し、冷静沈着な行動をさせる。 |
|
7 要救助者を救出するときは、進入隊員の負担を軽減するため昇降機等の機械力や他隊員の確保等により行う。 |
|
8 狭い進入口から槽内に進入するときは、進入前に呼吸器の吸気管がねじれないようチェックするとともに、呼吸器を吊り下げるときは確保ロープを取り、面体の離脱がないよう救助隊員の動きに合わせて慎重に行う。 |
|
9 槽内では無理な姿勢での行動が多く、足元も見えにくいので、転落防止に注意する。 |
|
10 タラップを利用し進入するときは、湿気でぬれていることがあるので、確実に手すりを握り、足元の滑りに注意する。 |
|
11 横穴に進入するときは、確保ロープを張らず緩めずの状態で設定する。 |
|
12 井戸内へ進入するときは、積み石の崩れあるいは経年劣化によるコンクリートの崩壊等に注意し、必要人員以外は近づけない。また、揚水設備がある場合は、感電事故を防止するため、電源の遮断を確認してから進入する。 |
|
13 人が立って活動できない横杭やトンネル等で、幅が狭く長いものにおいては、隊員の移動や資機材の搬送、要救助者の救出時に作業用台車や背板を使用する。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |
(2)救出活動
| 留意事項 | 事故事例等 |
|---|---|
1 複数のロープを使用することが多いので、つまずきや絡み等に注意する。 |
|
2 合図、脱出方法を確認後、進入させるとともに、確保ロープを含めロープの色分けを行い、管理の徹底を図るとともに、ロープの整理を確実に行う。 |
|
3 複数の隊員が狭い槽内等で活動するときは、呼吸器のボンベ等で他の隊員の身体や面体を強打しないよう注意する。 |
▶ 古井戸内で要救助者を吊り上げ救出中、結着していたロープがはずれて、井戸内で活動していた隊員が頭部を負傷した。 |
4 槽内からの救出は、機器の整理及び進入統制を徹底し、二次災害を防止するとともに、緊急時に備え予備の進入隊員を待機させる。 |
|
5 ロープで要救助者を引揚げ救出するときは、確実に結索し、また原則として救出中は要救助者の真下に位置しない。 |
|
6 救助のために使用する支点は、隊員が進入又は要救助者の引き上げに十分耐えられる材質、強度のある工作物、施設及び救助資機材を活用する。 |
|
7 井戸等においては進入口周囲に足場板等を敷き、内部の崩れ及び上部からの落下物を防止し、進入隊員の安全を図る。 |
|
| ヒヤリハットDBへリンク |